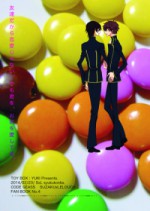◆ノンケスザクとガチルルちゃん。(R18)/SAMPLE◆
※ダブスタ常備。時系列については深く考えないで下さい。
「男が可愛いなんて言われて喜ぶ訳ないだろ」
その台詞と共に床に突っ伏す男の髪を引き上げた。軍の生活に不満がないとは言わないけれど、一番腹が立つのは何といってもコレだ。ブリタニアの差別など日常茶飯事、本当の敵は仲間である日本人の中にもいる。
腹を押さえてうずくまっていた男をもう一度蹴り飛ばした。見える所でやれば目立つから陰でこっそり。こういう考え方が僕は大嫌いだ。やらなければやられる、そういう価値観も本当は好きじゃない。でもお前がそのつもりならこっちも容赦はしない。昨日同じ部隊に配属されたばかりの男は低い呻きを残し、ぼろきれのようにぐったりしてそれきり動かなくなった。
宿舎で同室になり、夜になってからこいつは伸し掛かってきた。やたら愛想が良かったのはそういうことだったのかと納得するなり頭に血が上った。人の親切を逆手に取るなんてますます許せない。騒ぎにならないよう内々で済ませるために、部屋の外に出て警備という名の見張り役に幾らか掴ませておく。本当は聞こえているのに助けに来なかったんだからこいつも同罪だ。卑怯者め、と心の内で罵りながら紙幣を渡すと、守衛のブリタニア人はにやにやしながら受け取った紙幣を翳して見せた。
僕の金じゃない、そこに転がっている変態の金だ。
もともと同性愛者に偏見はなかったのに、軍に入ってから唾棄したくなるほど嫌になってしまった。自分もイレブンとして差別される側だ、同じように差別される辛さはよく解る。
でも、少なくとも僕は生きていく上で誰かに迷惑をかけてはいない。自分の暴力的な面を抑え込むために性格だって変えた。他人から見た自分がどう映るのかまでは解らなくても努力はしているつもりだ。
『イレブンなんだからブリキどもにも掘られてるんだろう?』。そんなことを言うくらいなら軍になんか入らなければ良かったんだ。風紀が乱れる、欲求不満ならそういう所に行けばいい。手近な僕で済ませようなんて考えを起こすからいけないんだ。
こういう揉め事はよくあることなので幸い大きな問題にはならなかった。黙認がまかり通ってしまう社会、やっぱり間違っている。内側から変えていくべきだという思いはますます強くなった。
僕に手を出してきた変態は軽い処分で済み、今も同室でのうのうと生活している。部屋を替えてくれという僕の訴えは当たり前のように退けられた。……やってられない。
いつ行っても人っ子一人いないカウンター。夜になるとバーになるその店の片隅には仕切り付きの卓が一席だけある。
そこのランチが美味いんだ、と言ってルルーシュは学校を抜け出していた。ついて行く僕も僕だ。結局二人揃って午後からの授業をエスケープする羽目になった。
ノンケに手を出そうとするゲイなんか全員滅べばいい。食後にそう切り出した僕にルルーシュは頬杖をつき、軽く肩を竦めて悪意なく言い放った。
「俺は解るけどな、そいつの気持ち」
「――は?」
耳を疑いそうになった僕の気持ちを解って欲しい。
「何が解るんだ?」
殺気立ちながら尋ねると、ルルーシュは「だから」と言い置いて誘惑するような仕草でテーブルの上に乗せていた僕の手を握った。
「お前みたいなイイ身体してる奴と同室なんだろう? 変な気を起こすのも無理はない」
ガタッと椅子ごと退いた。ルルーシュは一人納得するように深々と頷いている。
誰だろうこれは? そう思ったのは一瞬で、キラリと光る猫のような目付きを見てルルーシュはあの変態の味方なんだと悟った。
――完全に引いた、ドン引きだ。
顔面を引きつらせる僕にふっと微笑み、ルルーシュは困った奴だとか口走りそうな顔付きでゆったりと足を組み直した。困った奴は君だし困っているのは僕だ。余裕ぶった態度を見て確信する。
獅子身中の虫。親友だと信じていたルルーシュもゲイだった。
「冗談きついよ」
「まあ同情はする」
だったらやめろ、今すぐに。そう思って握られた手を跳ね除けける。ルルーシュは途端にムッとした。