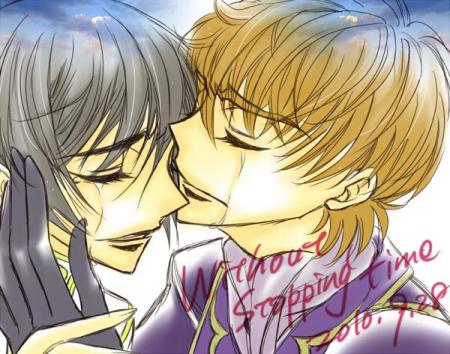SOSとポーカーフェイス 2(END)
※畳んでませんがBL的表現がありますのでご注意下さい。
キッチンに立ったルルーシュは、カップとソーサーの乗ったトレイを調理台の上に置き、ケトルで湯を沸かし始めた。
小型のケトルはすぐに軽快な音を鳴らし始める。ルルーシュは空のポットを軽く濯いでから湯を流し込んだ。
戸棚から紅茶の缶を取り出し、ティースプーンの反対側を梃子にして蓋を開ける。かこん、と控えめな音を立てて開く蓋。傍らに置き、火を止める。
温まったポットの湯を捨て、掬った茶葉をさく、さく、とふた匙入れたところで、ふとその手が止まった。
――カチャリ。
そっとスプーンを置いたルルーシュは、台の上に手をついたまま暫くぼんやりしていた。そうして、横に置かれたままのトレイを見る。
普段は二組。今日は三組あるカップとソーサー。そのうちの一組を取り上げ、シンクに置こうとした手がまた止まった。カップの取っ手に指を掛け、どうしようかと悩む素振り。
ちりん、ちりん、と涼やかな音色が響いた。鳴っているのは入れっぱなしにされているスプーンだ。
ソーサーに乗せたまま、ゆらり、ゆらゆら。
繋いだ手を揺らすように右へ左へと動かすたび、くるくると縁を滑るスプーン。抜き取ったそれを横に置いてから、ルルーシュはようやくカップを取る。
そんなルルーシュの後姿を、スザクはキッチンの入り口に突っ立ったまま黙って見つめていた。
気配を殺すのはスザクの特技だ。幼い頃から鍛錬を積んできた成果かと問われればそうかもしれない。
結局、スザクは帰らなかった。一度場を辞してから引き返してきたのではなく、単に気が変わっただけだ。
キッチンへと向かったルルーシュの真意を、スザクは知らない。懇意という域をはるかに超えた付き合いとて秘密は付き物だ。人の心底を確かめるなど容易なものか。それがルルーシュであれば尚のこと。……所詮、何もかも只の想像だ。
だからスザクはやって来た。ルルーシュを追って。
そして今、声も掛けずに素の姿を見守っている。
こちらに背を向けているルルーシュはスザクに気付かない。後ろで見られているとも知らず、カップを持ったまま動かなかった。
その中身が空だとスザクは知っている。何故なら、それは自分が使っていたものだから。
紅茶に砂糖を入れるのはスザクだけだ。ナナリーはミルク。ルルーシュはストレート。底に溜まった砂糖をかき混ぜながら飲む癖も、使い終えたスプーンを入れたままにしてしまう無作法も、今まで幾度注意されてきたかわからない。
ポットならとっくに温まっているだろう。紅茶を淹れるには頃合だ。茶葉だってもう入っているのに、何故湯を注がない?
空のカップに、一体何の用がある?
持ち上げたカップをルルーシュはじっと見つめていた。
……やがて、顔に近付ける右手の動きに伴って、僅かに頭が揺れる。
(―――!?)
言い得ようのない衝撃に襲われ、スザクは目を瞠った。
(今、何をした……?)
見間違いではないのか? あのルルーシュが。
それは、ほんの一瞬の出来事。――まるで、無声映画のワンシーンを見ているようだった。
緩慢な動作でカップを下ろしたルルーシュは、取っ手を持ったまま肩を落としている。手元のカップを一瞥してから、ゆっくりと下がっていく頭。襟足を覆う黒髪の下から真っ白な項が顕になり、細い肩を更に落としたルルーシュは長い溜息を吐き出した。
静かなキッチンに響く微かな空笑。……彼が、自嘲している。
(ルルーシュ)
心の中で呼びかけても声は出ない。指先がピクリと震え、ようやく正気に戻った。
スザクはただ、両の拳を強く握り締める。力が篭るにつれて、開いた唇から肺に冷たい空気が流れ込んできた。
たった今見たものは現実なのだと、スザクは急に意識する。まるで何事もなかったかのように、流れるような動作でカップを戻したルルーシュは、少し考えてからもう一度湯を沸かし始めた。
暖める前に濯ごうとカップに伸びかけた手が、また止まる。
ルルーシュが取ろうとしていたのはさっきまで触れていたものだ。素早い手つきで別のカップを選んでトレイから目を背けたのを見た瞬間、気付けばスザクは無意識に一歩踏み出していた。
水道の蛇口に伸びたルルーシュの腕を取り、背後から強く抱きしめる。
「……!!」
腕の中で、ルルーシュが声も無くビクリと震えた。
本当に驚いた時、人は叫ばない。恐怖を認識してから紛らわすために叫ぶ。
巻きついてきた腕をそろそろと見てスザクだと気付いたのか、ルルーシュは辛うじて落とさずに済んだカップを置こうと腕を伸ばした。
スザクはほとんど毟り取るような勢いでカップを奪い取り、遠くの方へと押しやった。荒々しい動作に驚いたルルーシュが怖々と振り返ってくる。
大きく見開かれた紫玉に映る純粋な驚きと戸惑い。――そして、疚しさ。
目が合った瞬間、理性が飛んだ。
ものも言わず噛み付くように口付けたスザクは、たたらを踏むルルーシュを台の上へと押し倒し、手首を掴んでより深く唇を重ね合わせる。
息の根も止まるような激しいキス。この人の全てを奪い尽くしたいと心の底から思った。
ルルーシュはされるがまま抵抗しない。唇をぴったりと塞がれ、一度も離されることなく深い口付けを仕掛けられているのに、いっそ健気なまでに受け入れ続けている。
掴んでいた手首から強張りが解け、掌が緩んだ。全身が弛緩すると同時に膝から崩れ落ちていくルルーシュの腕を、スザクは自分の首へと回させる。
首筋を通って背中へと縋る腕。かき抱いた背に爪を立て、溺れて救いを求める者のようにルルーシュはしがみ付いてきた。
重なり合った胸で感じる互いの鼓動。決して一方的な行為ではないのだと許されている。
その事実は、スザクの欠けた心を熱く満たした。
きつく抱きすくめたルルーシュを持ち上げ、開かせた二の足の間に膝を割り入れれば、ちょうど太腿に跨る形になったルルーシュの腰がもどかしげに蠢く。掠めた箇所は既に反応していて、少し押し当てるだけで鼻に抜けるような甘い吐息が零れ落ちた。
キッチンに響く荒い息遣い。密やかな衣擦れの音とくぐもった声。
……神経の焦げ付く音がする。
長い長い口付けの後、ゆっくり離した唇との間に伸びる透明な糸。もう一度噛み付くように口付けた瞬間、酷く感じ入ったルルーシュの顔が見えた。
深く絡めた舌を味わいながら、スザクは思う。
誘われる。幾らでも。際限もなく。だが、こうして求めてしまうのは果たしてルルーシュのみの咎なのか――違う。では、追憶から成る思慕か、慕情か。それとも全部か。
あってはならないものだろう、それは。一方的な情によって父親を殺め、罪を背負った自分には。
何のために規律の中へと身を投じた? 自らに贖罪を課したのは何のためだ?
仮にこれが疾うに禁じられた感情であったとしても、よもや純粋な恋情などではありえまい。雄としての本能がそれを否定するばかりか、混沌さながらに絡み合った糸は縺れに縺れて、今や元の形になど戻せもしない。
再会なんかしなければ良かった。終わらせるには、断ち切るしか。
だが、出来るのか。……答えは常に否だった。
彼は己を忌んでいる。嘗て「要らない皇子」と捨てられて、相変わらず孤独ばかり選ぼうとするルルーシュ。
思い出に捕らわれる心の根底にあるもの。その正体をスザクは知っていた。だからこそ揺らぐ七年前の誓い。――自分が傍にいなければ。
でも、本当は解放されたい。昔と違う自分になりたい。早く、早く。
彼のことをどうでもいいと思えるようになれたら、どんなに楽だろう。
共に居れば引き摺られそうになる自分がいる。今でも、こんなに。彼が望むなら、どんな願いでも叶えてやりたくなる。求められれば抗えない。求められなければ余計。
今だって、自制されれば結局こうして駆けつけてしまうのに。
駄目なのだ、それでは。そんな自分であってはいけない。……だから、本当はいつも必死の思いで押さえつけている。
今出来ずにいることが、これから出来るようになるものか。こんなにもよく、彼のことを解っているのに。――ああ、誰か。
再会した彼は過去の写し身。鏡に映る似姿。そんなはずはない。自愛ほど不可能なものに溺れる筈などないのだから。
似ている? いや、似ていない。
そんな彼に、何もかも奪われ壊され食らい尽くされる。奪い尽くしたいと願うのは己とて同じなのに、それですら……いや、今となってはそれこそが最大の恐怖だ。
幼少時からずっと、きっと、この身一つや人生ばかりか、命でさえもいずれ。たとえこの先誰が現れたとしても、きっと最後には。そんな予感がする。
――それなのに、こうして縋ってくる腕にしか満たされないのは何故?
解放されたルルーシュが、ぐったりと肩に額を乗せてくる。甘える仕草に増す愛しさ。甘えるな。甘えないでくれ。同じことを繰り返すわけにはいかないんだ。……そう思うのに。
罰を求める心とは相反する感情に引き裂かれそうになりながら、スザクは肩口に埋められた顔が僅かに傾いてくるのを待った。
向けられてきた頬に送るのは慈しみのキス。常の通りに流される。――彼だから。……彼にしか。
こんな風に、いつも内側から壊されていく。
ルルーシュは再び肩口へと顔を埋めてきた。多分これから言い辛いことを口にするつもりでいるのだろう。
そんなことでさえ解ってしまう。まるで遺伝子に刻み込まれた覚書。呪いのように繰り返す過去と今。
けれど、捕らわれてはいない。
(だって、もう“僕”は違うから)
こうして免罪符を振り翳す愚かしさ。それは宿命。ないしは何?
いつまでも続く訳ではない。この関係は。
(だって、僕はいずれ死ぬ)
だから、それまでは。
安心。慢心。逃げた先で気付く足元の鎖。
もしかすると、いずれそんな日が来るのだろうか? 漠然とした予感にスザクは震撼する。
甘く感じられるからこそ、これは毒だ。
でも知っている。気付いている。毒そのものに罪など無いと。
「……帰ったんじゃなかったのか」
か細い声で告げられたのは、予想に違わぬ質問だった。
「それよりも訊きたいことがあるだろ」
黒髪に鼻先を埋めてから頬をすり寄せたスザクは、ちょうど口元から近い場所にある耳朶に噛り付く。
「……っ」
逃れようと肩を竦めながらも、ルルーシュは顔を上げてはこなかった。ただじっと息を詰めながら耐えている。
幼い頃からルルーシュはいつもそうだ。石のようにうずくまり、耐える。堪える。我慢する。いつか壊れてしまっても、彼は「助けて」とは言えない。
そして、スザクはそんなルルーシュに苛立ちながらも翻弄され、いじらしく思う気持ちを抑えられないのだった。これも、幼い頃からずっと。
首筋に絡む腕の力が増し、より強く顔を押し当てられると、どうしようもなく狂おしい想いが湧いてくる。一体どこから――? 全身の血液が熱く沸き立ち、触れ合った箇所から肌が粟立つ感覚。
両肩に掛かるルルーシュの重みに、ほんの刹那「離れたくない」とスザクは願った。出来ることならずっと、いつまでも彼とこうしていたい。
歯止めが利かなくなりそうな衝動を抑えて食んでいた耳朶を離す。……その途端、耳がおかしくなりそうなほど甘い吐息が聞こえてきた。
深い酩酊。陶酔。
溺れるとは、こういうことを言うのだろうか。
「お前……いつから見てたんだ?」
ぼそっと尋ねてくる声は相当不機嫌だった。只の照れ隠しだとすぐに解る。
(もう気付いてるくせに)
カップは手なんか繋いでくれないし、キスもしてはくれない。
余程そう言ってやろうかと思ったが、さすがに意地が悪いだろうか。一応ルルーシュの心情を慮ってやめておく。
その代わり、
「ナナリーに言ってきたんだ。やっぱり昼食が終わるまで一緒にいてもいいかって。……だから」
「…………」
答えを待つルルーシュに一呼吸置いてから、スザクは耳元で告げてやる。
「続きは、そのあとで」
「―――っ」
耳の奥に流し込む。これもまた毒だ。
腕の中の細い身体が強張った。ぎゅっと握られた手に口元が緩む。どんな顔をしているのか早く見たい。そう思う自分にさえ漏れる嘲笑。
けれど、焦りは禁物。何故なら彼は、とてもナイーブだから。
「お前……仕事は?」
「僕がしたい。それじゃ駄目か?」
「……どうして」
「どうしてだと思う?」
ほとんど答えを言ったも同然だ。
尋ねられたルルーシュの腕が弱まり、胸元へと下りてくる。
きつく布地を掴む手で示される羞恥。スザクにとっては故意であるからこそ、同情を禁じえない。
「悪趣味だな」
「そうかな」
「そうだ」
シャツ越しに伝わる睫の感触。ルルーシュはさぞかし困った顔をして瞬いているのだろう。……きっと、眉間にも気難しげに皺を寄せて。
「ルルーシュは?」
「え……?」
「僕としたい?」
「――――」
ようやく見上げてきた紫玉が惑いのままに逸らされてゆく。至近距離から見下ろす睫は本当に長くて、いっそ作り物めいてさえ見えた。
「俺は―――っ」
ルルーシュの答えを待つことなく、スザクは襟元から覗く細い首筋に吸い付いた。
身を捩らせるルルーシュの頭を抱きかかえ、逃げられないよう固定する。
呻きと共に上がっていく顎と、顕になる白い喉。反った背を抱き寄せると胸が押し当てられ、無意識に引けた腰が跨った太腿から膝下へとずり落ちていく。
「っぁ!」
割り入れていた膝に前部を刺激されたルルーシュは、辛そうに腰をビクンと跳ね上がらせた。
スザクはその間も唇を離さない。さながら野犬がとどめを刺すが如く、剥き出しにされた其処に赤い鬱血の痕が浮かぶまで。
スザクに解放されるや否や、よろめいたルルーシュは調理台の上に後ろ手をついた。腕に掴まったまま台を背にずるずると崩れ落ち、とうとうその場に座り込んでしまう。
「驚かせてごめん」
折り曲げた片膝を立て、ルルーシュは荒く息をつく。吸われた首筋を押さえる手が細かく震えているのを見て、傍に屈み込んだスザクは柔らかな頬に優しく唇を落とした。
「……先に行ってるから、早くおいで」
そう言い置いてから立ち上がると、ルルーシュが悔しげに見上げてくる。目が合うなりぎこちなく逸らされ、つい微苦笑が漏れた。
「ナナリーと待ってる」
後ろめたそうに俯くルルーシュの顔に、ほんのりと朱が上る。潤んだ眼差しに淡く色付いた頬。落ち着くまでには、まだ少し時間が必要だ。
キッチンから出る間際、スザクは恨めしそうにこちらを見ているルルーシュへと笑いかけた。
完全に乱されたポーカーフェイスに、やはり満たされた思いを感じながら。
そうだ。毒花はこんなにも美しい。
罪はなくとも、やがては手折られる運命。
スザクは多分、その悲しさを愛している。
ルルーシュ陛下二周忌追悼イラスト(携帯用)

こちらは携帯用です。
フリーイラストですのでご自由にお持ち帰り下さい。
ルルーシュ陛下二周忌追悼イラスト。
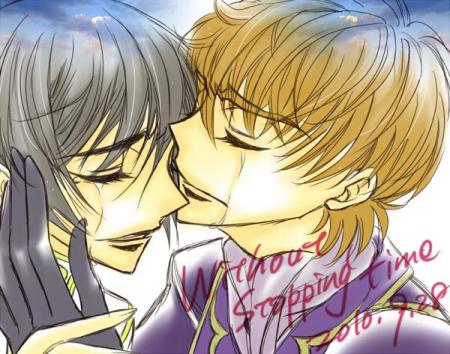 あの空の上で待ってる。
あの空の上で待ってる。
+++++++++++++++++
期間限定フリーイラストですのでご自由にお持ち帰り下さい。
(再配布はご遠慮下さい)
大きいサイズはこちら→
★ (600×473)
拍手コメレスです。
お返事遅れてすみません;;
反転してます。
M様>
ご意見&もったいないお言葉どうもありがとうございます(`・ω・´)♪
目次作ってみたのですが、見辛い的ご意見等ありましたら是非言ってやって下さいませ^^
長編はまだ最終話まで仕上がっていないのですが、あと数話で完結の予定です。
まだまだ毎日もえていますので、スザルルし続けていく所存ですvv
夏風邪のルルーシュ 6(END)
ほんのりと暖かい……。これは、何だ……?
背筋を辿る柔らかな生地の動きにつられて、意識がゆっくりと浮上する。
これは、もしかして濡れタオルだろうか。汗のべとつきが取れて、肌がサラサラした感触に戻っていくのが何とも心地いい。
まだとろとろと重い瞼をようやくの思いで開いてみると、まず真っ白なシーツが視界に飛び込んできた。パリッと糊の効いたシーツ。いつの間に眠ってしまったのだろう。
うつ伏せになっていた俺は、どうやら誰かに体を拭かれているようだ。
「ルルーシュ? 起きた?」
「……?」
まだ覚醒し切らないうちに声をかけられ、俺はぼんやりと横を見た。
「スザク……?」
舌が縺れて上手く言葉にならない。呂律が回らないのは顔の下半分がシーツと密着しているせいか。それとも、単に寝起きで頭が回っていないせいだろうか。
タオルを片手ににっこりと笑ったスザクの足元には、使用済みらしいシーツの白い塊が落ちていた。その横に置かれているのは、ごちゃごちゃと物の詰まった大きめのバスケット。
「君が寝てる間に全部取り替えておいたよ。どこか気持ちの悪いところは無い?」
強いて言えば、喉が痛い。水を飲みたい気もする。……そういえば、足腰が異様にだるい気がするのは何故だろう?
と、そこまで考えてから俺はようやく思い出した。寝落ちるまでの嬌態を。
「――っ!!」
がばっと跳ね起きた俺は、自分が一糸纏わぬ姿であることに気付いた。何故……何故裸? そうだ。俺はスザクと……。
思い至るなり俺は布団を手繰り寄せ、露出した肌を慌てて隠した。女じゃあるまいしと自己嫌悪に陥りそうになりながらも、状況を思えば仕方がないと無理やり自身を納得させる。
スザクはあたふたと布団をかき寄せる俺の姿を見て、苦笑しながら何かを差し出してきた。
「はい、これ。体も拭いておいたから、そのまま着ちゃっても大丈夫だよ」
綺麗に折りたたまれた衣類。スザクに手渡されたのは新しいパジャマだった。――それから、下着。
「お前っ……!」
今ので完全に目が覚めた。
拭いたってどこまでだ。もしかして全身か!? 気付くなりカッとなった俺はスザクを仰ぎ見た。
妙にさっぱりしていると思ったらそういうことか。……最悪だ。既に全身の至るところまで見られてしまっているとはいえ、まさか後処理までされてしまうとは。
そのパジャマにしたって、一体どこから出してきたとか、いつの間にとか、言いたいことは山ほどある。
だが、今はそれどころじゃない。胃薬を飲ませると見せかけて無理やりキスを仕掛けられ、訳の分からない理屈を展開され、挙句の果てにあんな……。
スザクは苦笑を浮かべたまま「やっぱり怒ってるよね」と肩を竦めている。
「ごめん」
「だからって謝るなよ」
思い返しただけで顔から火が出そうだ。とんだ醜態。よりにもよってスザクと……。
しかし、謝られたところでもう遅い。全ては終わったことだ。まさかあんなことになるとは思っていなかったものの、流された俺にも非はあるだろう。
とはいえ、未遂で済む雰囲気では決して無かったが。
スザクは畳まれた寝巻きの上から下着を退かし、取り上げたシャツを広げて俺の肩にそっと被せてきた。
「僕は後悔してないよ」
ぽつりと漏らされた一言に、思わず空気を読めと叫びたくなる。
「誰もそんなことは訊いていない!」
「うん。だからね、僕が言いたいのは君を抱いたことを謝ってるんじゃなくて、乱暴な抱き方してごめんって意味だ」
「……それだって、別に謝られたところでどうなるものでもないだろ」
「まあ、そうかもね」
シャツの合わせを握り締めたまま俯いている俺の横にスザクが腰掛けてくる。
なんだって突然横に来るんだお前は。椅子にでも座っていればいいだろう。
ベッドが体重で沈むなり、俺はつい焦って距離を置いてしまった。少々露骨な反応だっただろうか。反射的な行動とはいえ、幾らなんでも意識しすぎだ。
「さっきは君があまりにも可愛くて……それで加減出来なくなっちゃったんだ。謝るよ。本当にごめん」
隣に座ったスザクも気まずいのか、視線がやや余所の方に向いている。俺と会話しているというよりも、まるで独り言でも喋っているかのようだ。
「可愛いって……お前な」
「本当はもっと優しくするつもりだったんだけど、君も僕と同じ気持ちなんだと思ったら止められなくなっちゃって。次からは気を付けるよ」
「―――!?」
さらりと言ってのけられたスザクの台詞に、俺はピシリと凍り付く。
……こいつは今、なんと言った?
「次?」
「えっ?」
何を当たり前のことを、とでも言いたそうな顔でスザクが俺を見る。
こいつは次があると本気で思っているのか? いや待て、その前に――。
「本当なのか?」
「ん、何が?」
「だから、お前がその、俺のことを……」
「ああ、好きってこと? 本当だよ?」
「――っ!」
これもまた当然の如くさらりと言い切られ、俺は二の句を失った。覚えのある眩暈に再び襲われ、世界がくらりと反転する。
ただの悪夢かと思っていたが、どうやら夢ではないらしい。最早ここまで来れば諦めの境地といった心境ではあるが、俺の気持ちを知ってか知らずか、スザクは実にしれっとした顔で続けてくる。
「じゃなきゃ君相手に手なんか出さないよ。関係がおかしくなっちゃうだろ?」
「それは……そうだが」
実際おかしな関係になってしまっているというのに、開き直って言うことではないだろう。
大体、なんでこうなる?
俺は正直困惑していた。再会してからのこいつは、確かに俺と深く関わることを避けているように思えていたのに。
「お前の気持ちはともかくとして、俺はまだ応じるとも何とも……。それなのにお前は……」
「うん、そうだね。確かに一方的すぎた」
言うなりスザクは俺との距離を詰めてきた。咄嗟に逃げを打ったものの、下肢を覆っていた布団がもたついて上手く動けず、俺は後ずさった勢いのまま横向きに倒れた。
「……っ、おい」
顔の横に置かれた手に気付くと同時に視界が暗くなり、言い得ようのない恐怖が込み上げる。
また、何かされるのだろうか。
さながら肉食獣に追い詰められた獲物の気分だ。普通に話せば済むことだろうに、スザクは腕立て伏せのような体勢になって俺に圧し掛かってくる。
「言って、ルルーシュ。僕が好き? それとも嫌い?」
「――――」
身構えた俺は、肘を付いたままスザクを見上げた。真正面、それも超至近距離から見下ろしてくる一対の深緑。
意識が落ちるまでの出来事が一気に蘇り、羞恥だけで俺は死にそうになった。
大体なんで、その二択なんだ?……混乱する。両サイドには腕が聳え立っていて逃げ場は無いし、布団越しに下肢が触れるだけで緊張が走る。
キスされた時と同じ体勢。とてもではないが、熱っぽく射抜いてくるスザクの眼差しを正視出来ない。さっきから何とかして目を逸らそうとしているのに、俺はどうして出来ないんだ? スザクは何故、こんな目で俺を見る……?
「言わなくてもいいって、言っただろ……」
ずっと硬直し続けていた俺は、気力を振り絞ってようやくスザクから顔を背けた。――近すぎだ。こいつだって、俺が警戒していることくらい気付いているんだろうに。
目を伏せていれば頬に吐息がかかり、背筋にゾクリと震えが走った。スザクはそんな俺の様子を見てクスリと笑い、尚も畳み掛けてくる。
「確かに言わなくてもいいとは言ったよ。でも、順番が違うのは嫌なんだろ? 君が流されてくれたことが了承の証なんだって僕は受け取ったけど……そう思ったのは僕の思い違いだったってことか?」
「…………」
「僕に触れられるのは、もう嫌?」
スザクが浮かべているのは見るも寂しげな微笑みだ。応とも否とも言えぬまま俺は口ごもった。不安げな声音にも関わらず、切実で真剣なその囁きはどこまでも甘くて――。
なあ、スザク。それは、あまりにも卑怯な尋ね方なんじゃないのか?
横目で伺い見たそこには、緩く弧を描くスザクの唇。そこで止まってしまった視線を、俺は逸らせない。
……早く、動け。でないと気付かれる。
どこ見てるの? とでも言うように、スザクの口角が釣り上がった。視界が翳り、掌が近付く。
「……っ!」
俺は一瞬息を飲んだが、スザクに他意は無かったらしい。俺の前髪を払って熱を確かめようと、スザクは額に掌を乗せてくる。
警戒が解けて、少しだけ気が緩んだ。今何度あるのかは解らないが、夕食の頃に比べればかなり楽だ。
少し落ち着いたことを察したのか、スザクの目元も和らぐ。
まだ薬が効いているんだろう。スザクに飲まされた薬も……。
暖かなスザクの手はやがて額の上を通り抜け、優しく俺の髪を梳き始める。激しい抱き方とは打って変わって繊細な手つき。一見がさつに見えるのに、そういえばこいつは昔から手先が器用だった。
壊れ物に触れるように扱われると、抵抗する気力ですら失せていく。髪を潜る指先が耳元を掠めた瞬間、ビクリと肩が強張った。
やがて、スザクに触れられた箇所が燃えるように熱くなる。
耳に触れたのは故意か。それとも過失だろうか。――わからない。
「お前は……いつもこういう手で女を落とすのか?」
「まさか。僕、自分からこんな風に迫ったことって無いんだけど」
迫ったことが無い? 嘘だろ。だったらいつもどうやって……。いや、別にいつもという訳ではないのかもしれないが、絶対初めてではないだろう、お前は。
特に含みを持たせたつもりはないんだろうが、スザクは何とも余裕な口ぶりだった。明らかに場慣れしているし、物慣れている。経験の差を感じさせられるのが何よりの証拠だ。
じゃあ、お前はいつも迫られる方か。
そう思った途端、胸にじわりと黒いものが広がっていく。――なんだ、これは?
「信じると思うのか? これで」
咄嗟に俺は口を開いていた。頭で考えるよりも早く意識を逸らせれば。……が、遅かった。
嫌でも気付く。今のは嫉妬だ。認めたくは無いが。
無言で唇を噛み締める俺を見て、スザクは幸せそうな微笑みを浮かべていた。クソ。何がおかしい。いちいち笑うなよ。
しかし、たった今まで腹を立てていた筈なのに、既に居た堪れなくなってきているというこの事実。別に俺が悪さをした訳でもないというのに、仕舞いには良心の呵責めいたものまで感じている。……本当に、理不尽なことこの上ない。
こいつにはつくづくペースを乱される。そう思いながら俺は嘆息した。
――それにしても、頬が熱い。
「ルルーシュ、顔、真っ赤だよ」
「調子に乗るな」
頬に触れようとしてきたスザクの手を、俺は即座に払い落とした。ペシリといい音がしたものの、スザクは然程痛くもなさそうだ。
今にも唇が触れ合いそうな距離。こうして見つめられているだけで緊張する。何をされるか解らないのに、顔に触れられるのはまだ抵抗があった。なにせ、相手が相手だ。
スザクは申し訳なさそうに肩を竦めてから、ふっと吐息した。
「ごめん。言葉の方は素直じゃないけど、顔には出るんだなと思って」
続けざまに図星を突かれて更にムッとくる。平静を装うにしても、さすがに顔色までは誤魔化し切れない。
叩かれたっていうのに、随分軽くあしらえるんだな、こいつは。それも余裕があるからなのか?
「簡単にごめんとか言うなよ。押してまかり通るって意味だろ、お前のそれは」
「そんな僕は嫌い?」
……その質問の仕方も相当卑怯だ。
年齢に見合わぬ大人びた表情。こうして未知の面を見せ付けられるたびに、全く知らない男と話している気分になってくる。
「まさかお前がこんな奴だったとはな。誤算だよ」
「驚いた?」
「……ああ。少しね」
再会してからはてっきり大人しくなったとばかり思って油断していたが、人の本質とは早々変わるものではないらしい。であれば、今後は認識を改める必要があるだろう。
そうだ、今からでも遅くはない。いや、充分すぎるほど遅いか……。
俺が苦り切った顔で答えているのにスザクは動じない。精一杯の虚勢を込めて睨んでみても結果は同じだった。
なんなんだよ……。俺の不快はお前の機嫌を上昇させるだけだっていうのか? そもそもスザク、お前はなんで笑ってるんだ。さっきからずっと!
まさかとは思うが、俺は馬鹿にされているのか?
俺がそんな疑問を抱くほどに、スザクは終始にこにこ顔のままだった。
「たらされてるって自覚は一応あるんだ? 嬉しいな」
「嬉しい? 何言ってるんだお前は。はぐらかすなよ」
遊びのつもりで手を出したのであれば、タチが悪いどころの話じゃない。
柔和な童顔は笑うと更に幼くなるくせに、こいつは時折平気で大胆なことを口にしては経験の豊富さを匂わせる。
俺と離れていた七年間がこいつを変えたのか。デリカシーの無さは変わっていないようだが、お前の身の上に一体何が起こったんだ?
「いいかスザク。『たらす』というのは『誑かす』って書くんだぞ」
「酷いな。僕だってそれくらい知ってるよ」
スザクは臆面も無く「でも遊びじゃないよ」と言い放つ。そして、たった今叩き落してやったばかりだというのに、渋面を作った俺の手を躊躇いもなく握ってきた。
こ、こいつ……全然懲りてない!
「お、おい!」
止める間もないとはこのことだ。スザクは取り上げた俺の手の甲へと恭しく口付け、返した掌にも同じように唇を落としてくる。
なんて気障な奴だ。男相手にすることじゃないだろう。
すると、スザクはちょうど俺の気持ちを読んだようなタイミングで告げてきた。
「同性だからどうとかじゃなくて、ルルーシュだからしたくなるんだよ。こういうこと」
「……はぁ?」
思わず間抜けな声が出た。一体どういう意味なんだ、それは?
こいつが予想の斜め上を行くのはいつものことだが、天然の考えることは相変わらずよく解らない。
「君に嫌われたとしても、僕の気持ちは変わらない。嫌なら本気で拒んでくれ。でないと嫌だとは認めない」
「勝手だな」
「そうかな? でも君だって、どうでもいい相手に流されたりなんかしないだろ?」
スザクは言いながら、もう一度俺の掌に口付ける。
見せ付けているつもりなのだとしか思えない艶めいた仕草。まるで、そういった行為の最中を彷彿とさせるような……。
お前、絶対わざとだろ。
俺に手を振り払われても、スザクは余裕ぶった態度を崩さない。自由になった手を再びベッドの上に付き、いっそ楽しそうにさえ見える顔で俺を見下ろしている。
一度行き着くところまで行ってしまったものの、俺はまだ男としての矜持を捨てていない。スザクの目つきに身の危険は感じるものの、押し倒されているようにしか見えないこの体勢にだってひたすら苛立ってくるだけだ。
非難の意味も込めて、俺はスザクを睨んだ。
風邪が悪化したらどうしてくれる。いい加減どけよ。シャツ一枚羽織っているとはいえ、俺はまだ裸のままなんだぞ。
「お前、いつまでこの体勢でいるつもりなんだ?」
「ルルーシュこそ、いつまで口割らないでいるつもり?」
「……どうしても言わせる気か?」
「言いたくなければ言わなくていいよ。でも、僕はルルーシュだから本気になったってこと。それだけは、改めて伝えておくから」
「…………」
――どうする。この状況を一体どうすればいい。
考えろ。こいつはブリタニアの軍人で、俺はゼロで……というより、この期に及んでまだ結論が出ないってどういうことだ? 答えなんかとっくに出てる筈だろ。
そうだ。この関係はまずい。だって、距離を置こうとしていたのはこいつだけじゃない。俺だって同じなのに。
「そういえばさ……」
「?」
「君、前に彼女がいるって言ってたけど……それ、嘘だろ」
「えっ?」
唐突に尋ねられ、更に混乱が増した。
スザク相手にいると言ったのは確かに嘘だが、何を根拠に言っているのかさっぱり解らない。
にっこり笑ってスザクは続けた。
「隠さなくていいよ。あれ、ホントは嘘なんだろ?」
「何故そう言い切れる?」
「君の反応見てれば解るって。キスもセックスも初めて。……違う?」
あからさまな単語に眉が寄る。察しの良さなのか只の勘なのか。おそらく両方だろう。
「ああ、確かに初めてだよ。友達に手篭めにされたのはな」
「手篭めって……人聞き悪いな。――で、どうなの? 本当は」
「…………」
既にバレていることについて嘘を吐き続ける意味はない。
それにしても、こいつは本当に悪びれないな。なんて図太い奴なんだ。寧ろ悪びれろ。少しは!
スザクの意図に気付いた俺は、忌々しげにチッと一つ舌打ちしてから渋々答えた。
「外堀から埋めるつもりだな、お前」
「正解。結構計画的だろ?」
「どうだかな」
「どうだかなって……じゃあルルーシュ、誰かとしたの? そういうこと」
「――そういう、こと?」
俺は一瞬呆けた後、ようやくその意味に気付いて頭が真っ白になった。
……まさか、「そういうこと」って、あれのことか――!?
かあっと赤面していくのが自分でも解る。以前スザクに言われた時は「そういうこと」の指す意味が全く解らなかった俺だが、実体験した今となっては察するに余りありすぎた。
そうか、そういうことってあれのことだったのか。……駄目だ。恥ずかしすぎてクラクラする。頭がおかしくなりそうだ。
スザクは茹蛸のようになっているだろう俺を不思議そうに眺めていた。「どうしたの?」と尋ねてきたが答えられそうにない。
「な、なんでもない!」
「そう? だってルルーシュ、顔……」
「いいから!」
「?」
狼狽する俺の様子を見てスザクは頻りに首を捻っていたが、如何せんこいつは異様に勘が良い。これ以上突っ込んでこられては堪らないとばかりに俺は話を逸らした。
「お前の言うとおりだ。本当に彼女がいたんなら、俺がお前に流されることはないさ……も、もういいだろ!」
これだけ言ってやれば充分だろうと思いながら、俺はやけくそのように叫んだ。
とことんペースが乱される。ただでさえ想定外の事態続きで混乱しているというのに、タイミング悪く薬が切れて熱も上がってきたようだ。
スザクは暫くの間ポカンとしていたが、満面の笑みになるなりぎゅっと抱きついてくる。「おい」と呼びかける俺の声と、スザクの「なあ、ルルーシュ」という呼びかけが重なったが、何故かスザクの声は限りなく低かった。
――何だ。その平坦な低音は。口調も若干変わったような……俺の気のせいか? 何か、とてつもなく嫌な予感がするんだが。
俺はそう思いつつ、お互いどちらともなく顔を見合わせてから口を開いた。
「……なんだ、スザク」
「彼女のでないなら、あの髪の毛は誰のなんだ? ルルーシュ」
――あ。
マズい。とてつもなくマズい。
「髪の毛……あ、ああ。あれはだな、その……」
「もしかしてギャンブル仲間、とか?」
「ああ! そう、似たようなもんだ。よく解ったなスザク。よく金だのピザだのせびりに来る女がいてな。多分その時に落として行ったんだろう」
「その人とはどういう関係? 賭けのお金でも貸してるの?」
「…………」
「ルルーシュ」
「――っ、そうだ! そいつは毎回一文無しで転がり込んでくるような女でな、断じて彼女とかそういう存在じゃない!」
自白を強要してくるスザクの真顔が凄まじく怖い。そして、腕の力が半端ではないのでとても苦しい。
限りなく嘘に近いが、一応嘘じゃない。脳内シュミレーションは完璧だ。
「ルルーシュ」
「なんだ?」
「君の人付き合いに関してあれこれ言うつもりはないけど、お金の貸し借りはよくないよ?」
だろ? と言いながらスザクは首を傾げた。そんな仕草ですら、今はもう凶悪にしか見えない。というか笑顔が怖い。無言の重圧を感じる。いや、威圧か。これは……。
それから、全体重かけて圧し掛かってくるんじゃない。重いんだよ! お前は俺を潰す気か!
「ルルーシュ」
「はい!」
「キスしてもいい?」
「はぁっ?」
直球な質問に呆れてしまう。
お前……さっきの今で、よくそんな台詞が出てくるな。一体どういう神経してるんだ? とはいえ、これは話題を逸らすための絶好のチャンス。
だが……!
「駄目だと言ったら?」
つい捻くれた返答をしてしまう自分に俺は泣きたくなる。
そう。しつこいようだが、これは最後の抵抗だ。スザクが相手である以上、牽制にすらならないかもしれないが……そもそも、俺にNOという選択肢などあるのか? この状況で。
一旦腕を放したスザクは、慈愛に満ち溢れた表情でこうのたまった。
「じゃあ、もうしない。君がいいって言ってくれるまで待つよ」
「嘘をつけ」
「うん。よく解ったね」
「――ぇ?」
朗らかな声と共に、俺の唇はスザクにあっさり奪われた。
――開き直ったスザクほど、俺の手に負えないものはない。
そうだ。スザクは絶対、俺の言うことなんかまともに聞きやしない。昔から……。こいつはそういう男だ。
唇が離されると同時に、スザクは言った。
「ルルーシュ。君の風邪が治ったら、二回目もしようね」
「……そういうことを、か?」
「うん」
有無を言わせぬ口調のスザクに抱きしめられた俺は、半ばぐったりしながら「好きにしてくれ」と呟く。
ああ。風邪なんか、本当にひくものじゃない。
特に、夏風邪は馬鹿がひくものだ。
SOSとポーカーフェイス(スザルル)
クラブハウスの一角。テラスに置かれたテーブルに椅子が三脚。
白で統一されたその上にはティーセットが置かれ、馨しいアールグレイの芳香を辺りに漂わせている。
スザクは手渡されたオレンジ色の折り紙で鶴を折っているところだった。テーブルに散らばる幾つかの完成品。花びらの形に口を開いた小さな箱に、愛らしい兎。
スザクは懐かしい日本の遊びに目を細めた。向かいで熱心に何かを折っているナナリーを見て、よく手を切らないものだと感心する。薄い紙の縁を辿る少女らしい小さな手。白く細長い指の形が、ルルーシュに良く似ている。
と、そこで、喜色を示したナナリーが「出来ました!」と顔を上げた。
「お兄様」
少し離れた位置で読書中だったルルーシュが、ページをめくる手を止めて振り返る。何ページかだけちらりと確認してから、栞も挟まず本を閉じた。
「何を折っていたんだ? ナナリー」
椅子ごとテーブルの方に移動してきたルルーシュへと、ナナリーが折り終えたものを差し出す。
「船なんです。見て下さい。上手に折れていますか?」
「ああ、すごく上手だよ。ナナリーは器用だな」
「ふふ、お兄様ほどじゃありません」
これが帆か? と尋ねながら、ルルーシュが尖ったヨットの先に触れている。
褒められてはにかむナナリーの可憐さが眩しくて、妹に微笑みかけるルルーシュの優しさが甘やかで、口元に笑みを刻んだスザクはそこから目を離すことが出来ない。
どこからどう見ても幸福そのものの光景。このまま時が止まればいいと願ったスザクの目線は、けれど下へと落ちていく。
軍務に空きが出れば学校へ。休日はクラブハウスへ。それがスザクにとっての『当たり前』であり『日常』だった。特に約束などしていなくても、半ばルーティンワークと化した日々のサイクルに疑問一つ抱くこともなく。
それくらい、スザクがこの兄妹と時を共に過ごすことは『普通』のことだった。昔から。
とはいえ、スザクからルルーシュに「行きたい」と強請ったことは一度も無い。頃合を見計らって「行ってもいいか」と尋ねるだけだ。
彼の方から「今日うちに来られないか」と誘われることもある。しかしスザクにとって此処へと訪れることは、どちらにせよ自分のためだけではないように思われた。
言ってみれば、身に染み付いた習い性のようなものだろうか。――『気遣う』という意味での。
互いに声を掛け合うタイミングというのがまた、いつも上手い具合にスザクの軍務との兼ね合いがとれているのも口実を作る一因になっている。……三人が、三人のままでいるための。
折りかけの鶴へと目を落としながら、スザクは思った。
何故こうも綻んでいくのか。何故変わってしまうのだろうか。まるで掌から零れ落ちていく砂粒のように。
スザクの懐には、七年前に時を止めた父の形見の懐中時計が仕舞われている。この時計の針と同じように、スザクの時もまた止まっていた。今と昔が違っていることを痛烈に知っていながら、心だけが置き去りのまま。
ずっと眺めていたいうつくしさは、刹那のものであるからこその尊さか。それとも、最早過去か虚構の中だけにしか存在し得ない輝きだとでもいうのだろうか。……認めない。守る立場に自らを置くと決めた以上、たとえ壊れかけの心であろうとも。
けれど、守ると決めた端から「理不尽だ」と叫ぶ声がする。己の内側から。
――何故だ。何故こうなった。あんなことをするつもりじゃなかった。してはいけなかった。でも俺はああするしかなかったんだ。ああしなければならなかったんだ。大変なことをしてしまった。今も沢山死んでいるんだ。今この瞬間にも誰かが死に続けているんだ。
沢山、大勢、殺してしまった。……俺のせいで。
知って欲しい。気付いて欲しい。出来れば今すぐにでも打ち明けたい。
ああ誰か。
助けて。ルルーシュ。
言いたい。でも言いたくない。言ってはいけない。言えば責めになる。お前のせいだと詰ってしまう。
――お前さえいなければ。
あの時、お前に頼まれたりさえしなければ、俺は――。
……こうやって、全ての罪をルルーシュ一人に負わせたがる醜い自分を殺しながら生きてきた。七年間、ずっと。
孤独というのは、一人きりでいる時には感じない。集団ないしは近しい者の中にあってこそ初めて感じるものだ。
だからなのか、この幸福の中に居ても尚、スザクは孤独だった。……愛しているのに。こんなにも。
心の中で裏切っているからこそ、せめて行動だけは。そうでなければ、今この場に居てもいい資格などどこにも無いのではないか?
罪滅ぼしのために更なる罪滅ぼしを重ねていく自分を、スザクはいつだって愚かだと思っているけれど。
「……スザクさん?」
気遣わしげな声がして、スザクは慌てて「何?」と答えた。
「どうかしましたか?」
「ああうん、なんでもないよ」
人の心の機微に敏いナナリーに気付かれまいと、スザクは努めて明るく振舞う。ナナリーではなく何故かルルーシュに向かって答えてしまったのは、彼が探るような眼差しをこちらに向けていたからだ。
――お前、何かあったのか?
ルルーシュは、そういう目でスザクを見ていた。
(何かあったとしたら、君はどうするの?)
一瞬だけ自分とルルーシュを比べようとしてから、スザクはすぐにやめる。
本当は、もう会わない方がいい。これ以上関わらない方がいい。でも、今更そうすることも出来ない。
身動き取れない現状の中、いつか破綻へと向かっていく予感だけをずっと感じている。……それも、そう遠くない未来に。
果たしてその時が訪れるまでに、自分は上手く死ぬことが出来るのだろうか。
この危惧が決して只の予感では済まないことに、スザクは気付いている。心の奥底をルルーシュに知られたが最後、今在る幸福は消えてしまう。同時に、万一スザクがルルーシュと心を共有し合うよう努めたとしても、やはりこの関係は終わってしまうのだ。
……それでも、スザクは未だに現状から目を逸らし続けていた。彼らが無事で生きていたと知ることが出来たのはこの上ない僥倖だったけれど、本当はこうして再会なんかしなければ良かったのかもしれない。
運命の皮肉を呪うとは、きっとこういうことを言うのだろう。
ルルーシュはどう感じているのだろうか。訊きたくても訊けないことでスザクの頭は常に一杯だった。
だからこそこうして隙間を埋め合うように、人目を忍んで肌を合わせることを選んだのだとしたら――。
(僕が『軍人は死ぬものだ』と思っていることを、もし君が知ったら)
スザクには解る。距離が近すぎるからこそ、解りすぎるくらいに解ってしまう。ルルーシュの行動も、その思考パターンについても全て。
もしもスザクが心の底で『贖罪のための死』を求めていることをルルーシュが知ったら、一も二も無く「軍など辞めろ」と言い張るだろう。
それどころか、もしかすると、力尽くで辞めさせようとすることさえあるかもしれない。
スザクの意思を無視することで自分が嫌われようとも構わない。何度断られようと絶対に説得し続けて、最後には必ず頷かせてみせると意気込んで――それが『管理』になってしまうことにも気付かずに。
真相を知らされれば彼は深く傷付き、どこまでも重く受け止め、一生をスザクに捧げるのかもしれない。
当然、二人の関係は変わってしまう。それも大きく。
けれどもルルーシュの場合、決してそれだけでは終わらない。おそらく自分が道を踏み外させた責任を取るという名目で、やはりスザクに干渉しようとするだろう。
スザクに罪を背負わせたのならば、償うに相応しい道を示すのが自分の罰。ルルーシュなら間違いなくそう考える。……どこまでも優しく、独善的な判断の下に。
だから駄目なのだ。ルルーシュには言えない。絶対に。
ルルーシュは、他人と自分とを同化させたい欲求が強い。
依存と支配は紙一重。過保護や過干渉はその第一歩でしかない。――これは、幼い頃から彼を見続けてきたスザクだからこそ言えることだった。
最初から何一つ打ち明けられなくても、打ち明けた上で拒否されたとしても、どのみちルルーシュは深く傷付く。
本当は、既に傷付いている。スザクが距離を取り続けようとすることに対して、「何も打ち明けてもらえない自分には友としての価値も無いのか」と。
違うのに。そうじゃないのに。
そんな反応、求めていない。ルルーシュに出来ることなど、本当は何一つ無いのだから。
彼は、ただ見ていてさえくれればそれでいい。お前なら大丈夫だと太鼓判を押して、朗らかに笑い飛ばして……どんと大きく構えていて欲しい。
いつ帰ってきてもいいように。
そして、もう二度と帰って来なくても、平気で生きていけるように――。
スザクがルルーシュに対して望むことはそれだけだ。……でも、ルルーシュには出来ない。彼だからこそ。
理由は、彼が誰あろう、ルルーシュだからだ。
道を誤ったからこそ、スザクはこうした道しか歩めない。でも、ルルーシュはそんな事実をきっと認めないし、受け入れることも無いだろう。
「ナナリー」
呼びかけてナナリーの手を取ったスザクは、折り終えた鶴を「はい」と掌に乗せてから立ち上がった。
うん、と伸びをしてから一言、
「まだちょっと時間早いけど、今日は僕、これで失礼するよ」
「あら、もう? 何か用事でもあるんですか?……もしかして、お仕事?」
「うん。午後からちょっと軍の方に戻らなきゃいけないから」
ナナリーが残念そうに見上げてくる。閉ざされた瞼に向かってスザクは笑いかけた。
胸の痛みで顔が曇りそうだ。シュミュレーターでの数値テスト。――本当は、どうしても今日こなさなければならない用事ではない。
ふと視線を感じて、スザクは笑顔を作ったままルルーシュを見た。
「気をつけて行ってこいよ」
ほぼ完璧なタイミングで告げられる。動揺は微塵も無い。
「技術部だもの、大丈夫だよ」
肩を竦めながらスザクが返すと、ルルーシュは一抹の寂しささえ滲むことのない――これもまた完璧なさりげなさで目元を緩めて空のカップへと手を伸ばした。
「ナナリー。お茶、新しいの入れてくるよ」
「はい。有難うございます、お兄様」
「じゃあスザク、明日また学校でな」
「うん、また明日」
スザクがにこりと笑い終えるところまで、ルルーシュはきちんと目を合わせてくる。わざとらしく愛想を振りまくでもなく、かといって、あてつけめいた刺々しさなど微塵も感じない。カップやソーサー、ポットやミルクピッチャーまでもをトレイに乗せ終える仕草に至るまで、何もかもが終始一貫してごく自然だった。
振る舞いは勿論のこと、端正なその顔に浮かべている穏やかな表情でさえも。
頬の横で揺れる黒髪。紫水晶のように煌く透明な眼差し。――綺麗だ、と素直に思う。
所作に一切乱れを見せぬまま、ルルーシュはスザクに背を向けた。わざと『戻る』と言ったのに、いっそこちらの気が抜けてしまうほどの素っ気無さ。……それだけが、スザクの胸に少し刺さった。
――俺は、お前のやろうとしていることに、文句なんか言わないよ。
それがお前の意思ならば、興味も過剰な執着も、全て消してみせよう。
お前が少しでも楽になれるのなら、俺に何をしようと構わない。
だから、お前がそんな意地悪言う必要なんか、もうどこにもないんだ。
行っていいよ。どこにでも。
俺は今までもこれからも、ずっとお前のことが好きだから。
たとえば、そんな献身。
牽制を口にした自分の方が、卑小に思えてしまうほどの。
キッチンへと向かう足取りですら淀みなく、優雅。
ただ彼は、まっすぐに背筋を伸ばして――。
(演技、上手いなぁ)
負け惜しみだと解っている。
だから、ルルーシュの姿が視界から完全に消えてしまうまで、スザクは彼の背中をずっと目で追っていた。
『完璧なものほど読みやすい』
いつだったか、そんなことを口にしていたのは誰だっただろうと思いながら。
+++++++++
SOSとポーカーフェイス と、『優しい嘘』
夏風邪のルルーシュ 5
※この先、大人専用です。
R20ですので折々してます。ご注意ください。
夏風邪のルルーシュ 4
※畳んでませんが、BL的表現有ですのでご注意です!
一見冷たそうにも見えるルルーシュの唇は、開かせてしまえばその中は驚くほど熱かった。
重ねた瞬間に気付いたのは、男の唇とはとても思えないほどしっとりと吸い付いてくる上唇の感触。薄いそれの先はまるでキスを強請るように形良くつんと尖っていて、それでいて下唇はふかふかと柔らかくて、正にかぷりと吸い付くのに丁度いい按配。
僕はちょっとした感動さえ覚えた。出来合いの凹凸だって、ここまで上手く重なることはきっと無い。
これは決してキスとかそういうのじゃないけど、誰かとこうして唇を重ねること自体久しぶりだった僕は、思わずこのまま食べ尽くしてしまい衝動に駆られた。……もしかして僕、欲求不満なのかな。
指先を掠める頬はすべすべしていて、小作りな顔と同じく捕らえた顎もすごく細くて、無理やり口を大きく開かせたりしようものなら壊れてしまいそうだ。
ルルーシュの目頭だけじゃなく、僕の瞼にもかかってくる黒髪の柔らかさ。石鹸の香りにも似た、仄かな体臭。
僕はその全てに酔ってしまったかのように、クラクラと眩暈がしてくるのを止められずにいた。
相手はルルーシュだと解っているのに、こみ上げてくるのは脳髄が痺れていくような深い陶酔。絡んだ吐息は熱っぽく、唾液に薬の味が混ざってしまうことだけが少し残念だった。
何もかもが、女の子とは全然違う。似ても似つかない。
女性は、ちょっと下品なくらいで丁度いい。勿論、そういう時だけは。
軍にいるとそういう誘いも多いから、これも付き合いだと思って割り切るより仕方ない場合もある。僕は自分から誘ったりは絶対しないし、今でこそ、そういうはしたないことはしないけど……。
でも、当時は「別に付き合ったりするわけじゃないんだし、相手がいいって言うなら別にそれでいいや」と思ってはいた。
女性特有の媚や浅ましさ。噎せ返るほどねっとりしたあの甘さ。
そういった行為の際に、僕が女性に対して一番可愛く感じるものは、実はそれだ。
当然、男のルルーシュにそんなものは感じない。それなのに、何故かずっとこうしていたくなるような……それどころかもっと奥まで荒らして、乱して、貪りたくなるようなこの感じは何なんだろう?
乾いた土に染み込んでいく水のような心地よさに、僕は当初の目的も何もかも忘れて、うっかりのめり込みそうになっていた。
適度に弾力があって、ふっくりしていて、それでいて滑らかで。
――ルルーシュの唇は、すごくすごく、気持ちがいい。
「うっ、んんっ……!?」
舌を深く差し込んで喉の奥まで錠剤を送り届けてやると、それまで呼吸することも瞬きすることも忘れて硬直していたルルーシュはぎゅっと目を瞑ってくぐもった声を漏らし、一瞬ビクリと肩を震わせた。
反射的に手が突き出されたものの、僕を遠ざけようとしていたその手は、絡み合う舌の感触に耐えるように僕の肩を強く掴むだけだ。
――飲んで、ルルーシュ。
僕がそう思いながらルルーシュの舌の上に落とした錠剤を舌先でコロリと転がしてやると、ルルーシュはえずくように顎を二、三度上下させてから、んく、と喉を鳴らしてコクリと薬を飲み込んだ。
僕は溶けた錠剤の苦味を散らすために角度を変えてより深く唇を重ね合わせ、絡めたルルーシュの舌から唾液ごと全て吸い取ろうときつく吸ってやる。
「んぅ、ん、ん―――」
鼻に抜けるような声を漏らしたルルーシュが、僕の下で首を振りながら逃れようとするのを、僕は逃さないよう素早く顎を固定して押さえ込む。
舌に残る苦味が全て消えるまで、僕は数回に渡ってルルーシュの舌を扱き続けた。すると、肩を掴むルルーシュの手がガクガクと震え出し、口の中で二度、三度と舌を動かすたび、痙攣するようにビクンと体が跳ね上がる。
「――っ、ぁは!」
ずっと呼吸を止めていたルルーシュは、口を離した瞬間喘ぐように空気を求めて唇を戦慄かせ、引きつけを起こしたような音を立てながら息を吸い込んでいた。よほど苦しかったのか、僕のシャツを握り締めたままもう片方の手で自分の胸元を掴み、かくん、と首を傾けてせわしなく肩を上下させている。
ルルーシュは、とろん、と蕩けた横目で僕を見た。悔しそうにも切なげにも見える眉の寄せ方。
それを見た僕の心臓が、ドキリと跳ねる音がした。
くったりと力の抜けたルルーシュの顔は、見ようによってはうっとりしているようにも思える顔だ。震える唇はまだ開かれたまましっとりと濡れそぼり、その隙間からピンク色の舌先を覗かせているさまは、僕の目には何故か酷く卑猥に映った。
唾液で濡れ光る唇に、ほんのりと薄桃色に染まった頬。
妖しく色付き、劣情を誘うように僕を見る目元。
澄んだ菫色の瞳には涙の膜が張り、眦からは今にも潤みが零れ落ちそうになっている。
そんな恍惚としたルルーシュの表情を見るなり、僕は自分の腰がずんと重くなるのを感じた。まずいよ。――そう思った途端、たてかましく脳内で警鐘が鳴り響く。
僕の理性が慌ててブレーキをかける中、今までずっと僕の肩を掴んでいたルルーシュの手が、急に力を失ったようにずるりとベッドに落ちた。
「嫌だった?」
「…………」
僕はおそるおそる訊いてみたけれど、ルルーシュは何も答えない。はあはあと息を荒げるばかりで呆然としているだけだ。
多分、答えたくても答えられないんだろう。たった今自分がされたことについて処理し切れていないのか、それとも動揺と混乱の中で思考が麻痺しているだけなのか、途方に暮れたように精気を失った風情でしんなりと座り込んでいる。
僕はごめん、と続けようとしたけれど、何も言えぬまま黙り込んだ。――ただ、濡れているルルーシュの唇に魅入られたまま、どうしても目が離れない。
殴られるかと思ったのにとか、どうして抵抗しないのとか、怒らないの? とか。ルルーシュに言いたいことは山ほどある。
でも、最早そんなことを言えるような雰囲気じゃなかった。
だって、何? その反応。僕そんなつもりじゃなかったよ。――これは、本当に本当だ。
すると、不意にひゅっと息を吸い込む音が響き、その次に、また引きつるような音を立てて息を吐き出す音が聞こえた。
「な……で……?」
「…………」
「……ザク……。お、おま……お前……。な、だ……? 今の……」
ルルーシュは震える声でようやくそれだけを言い終え、最後にはっ、と短く呼気を漏らした。
ショックが大きすぎて、呼吸さえ満足に出来ていないらしい。
そんなつもりじゃなかったとか、これは只の事故だとか、ほんの悪戯のつもりで仕掛けただけだとか、ましてや出来心でしたなんて言える状況でもなくて。
だって、こんな反応されるだなんて思ってもみなかった。本当に。
それなのに、僕の目はルルーシュの唇に吸い寄せられたまま、全然離れてくれない。
どうしよう。
――もう一回キスしたい。今のは絶対、キスじゃないのに。
僕は、怯えたように瞳を揺らしながら見つめてくるルルーシュを凝視していた。
なんで? 今、なんでって訊いた? こっちこそだよ、ルルーシュ。君、どうしてそんな風になってるの? 彼女いるんだろ? したことないの? こういうこと。
そこまで考えてから、僕は気付いた。
無いんだ。多分。っていうか、彼女がいるって言ってたこと自体、実は嘘?――まさか。でも、なんだってそんな嘘を?
「ルルーシュ」
気付けば僕は口火を切っていた。何を言うつもりかも決めないで。
「……?」
ほんの少しだけ正気を取り戻しかけたのか、ルルーシュが僕の呼びかけに一応ピクリと呼応する。――あ、まだ。まだ完全に正気には戻らないで欲しいんだけど。
ちょっと言いたいこと、あるからさ。
「君、彼女のこと愛してる?」
言いながら、あまりにも唐突な質問だと自分でも思ったけれど――でも、止まらなかった。
ルルーシュはそれにも一応反応し、「……ぇ?」と掠れた声で答えながら、脱力していた上半身を僅かに起こした。
僕はその様子から目を逸らさずに見守っていたけれど、ルルーシュは当然の如く呆けたままだ。いきなりすぎる質問に釈然としないながらも、何故今そんな話を振られているのか一生懸命考えているらしいことだけは辛うじて伝わってくる。
「あのさ、頼みがあるんだけど」
「――――」
ルルーシュが僅かに目を見開く。これから僕に何を言われるのか、全く予想出来てないって顔だ。
……まあ、当然だろうけど。
「彼女と別れてくれ」
「!?」
単刀直入な僕の台詞に、ルルーシュがこれ以上無いほど大きく目を剥いた。キスの理由も碌に説明されないまま、いきなりこんな台詞を突き付けられたら誰だって驚くよ。
――いや、だから。あれはキスじゃないってば。それより、僕は何を言っている? 一体何考えてるんだ? 彼女と別れろ?
どうして――?
ルルーシュは必死で襲い来る動揺と闘っていた。僕は、シーツをぎゅっと握り締めているルルーシュの手を見つめながら、間の抜けた自分の思考にすかさず突っ込む。けれど、何もかも自分でもよくわからない。
よくわからないまま、口に出すなよ。また失敗するぞ。
心のどこかから、そんな声が聞こえてくる。……ような、気が、した。けど。
――知るもんか。
「僕にしなよ」
いいや、言ってしまおう。そう思って口に出してから気が付いた。
「君が好きだ」
僕の、これが、本音なんだと。
「!!?」
ルルーシュはルルーシュで、きっと頭の中は大パニックだ。さすがにこれは、言われなくたって解る。
口に出す言葉を選ぶ余裕ですら完全に消失したのか、ルルーシュは口をぱくぱくさせたまま「あ」とも「う」ともつかない声ばかり発していた。
可哀相だな、ルルーシュ。
他人事じゃなくて、そうさせたのは僕だけど。だから、ちゃんと責任は取るよ。ちゃんと……ちゃんとね? いや、取らなきゃ駄目だろう。だって、もう冗談でしたで済まされるような空気じゃない――って、冗談で済ますつもりもないよな? 僕は。
それに、そもそも相手はルルーシュだし。
えっ? でも、ちょっと待ってくれ。この雰囲気って一体……。たかだかキス一つで?……いやあれはまだキスじゃないけど! でも、幾らなんでも流されやす過ぎやしないか?
僕じゃなくて、ルルーシュが。
――ん? そんなことより、僕、今なんて思ったんだっけ。ルルーシュになんて言ったんだっけ?……えっと、まだ?
まだキスじゃないって、どういう、意味……。
頭の中では精一杯混乱しまくっているのに、気付けば僕はまた、ルルーシュに真顔で言ってしまっていた。
「君も僕のこと好きだろ。彼女と別れて、僕にしろ」
えええええええええええ!?
ちょっと! ちょっと、待って! 待ってくれ! 何言ってるんだ僕、いや俺は!?
――と。
自分自身が発した台詞に思いっきり動揺した僕は、今まで無意識でルルーシュに言っていたことを数秒で把握し直し、その直後にようやく正気を取り戻し、気付けばふっと笑っていた。
なんていうか、突き抜けた。
つまり、自分に呆れたってことだけど。
「……そっか。解ったよ、ルルーシュ。僕は君が好きだ。君の風邪なら移されてもいいと思うくらいに。君が遠慮するなら無理やりキスまで仕掛けてしまうくらいに――僕は、君を可愛いと思ってる」
「―――――」
ルルーシュは案の定、絶句した。ルルーシュはルルーシュで、ショックとか衝撃とかいう領域を軽く突き抜けたみたいだ。
確かに、君の常識の中では、こういう事態は絶対に想定不可能だろうね。
あ。今、眩暈してるな、と思ったら、ルルーシュはこの世の全てに絶望したような顔であんぐりと口を開けた。そして、間の抜けた顔のままはたはたと瞬きを繰り返し――やっぱり、ぐらっと上半身が傾いた。
後ろ手を付いてぺたんと背後にへたり込んだルルーシュは、腰を抜かして完全に自失。その直後、見るも鮮やかにかあーっと赤面していく。
……首まで真っ赤だ。
見事だな、と妙に感心する反面、僕は思う。――完璧に大事故だと。
でも実は、いつかやるんじゃないかと思ってた。
だって……昔からずっと変だ変だと思ってはいたんだ。友達って、普通はこういう感じじゃないもんな。
少なくとも、こんなに密接した関係なんかじゃないってことだけは確かだ。
男の友達を、それが幾ら生まれて初めて出来た友人で、しかも幼馴染であっても、可愛いとかいじらしいとか思ってしまうなんて尋常じゃない。
だけど無理もない。
思えば、男だからとか女だからとかじゃなくて、ルルーシュはいつだってルルーシュだった。
……だから、いつかやるんじゃないかと思ってはいたんだ。ルルーシュと再会してしまってからは特に。
近付きすぎるのは危険。「いつか僕は、まともな道を踏み外すんじゃないのか?」って。
大体、僕も僕だよ。
なんで気付かないんだ? 『放っておけない』って、男が恋してる相手に対して使う最もポピュラーな常套句じゃないか。
ああ。すっごいスッキリした。ルルーシュに対してずっと感じてたモヤモヤが全部吹き飛んだ。
そっか、そうだったのか。僕、ルルーシュのこと好きだったんだ。そういう意味で。
ずっと保護者か兄弟か身内みたいなつもりでいたけど、ルルーシュは友達であって友達じゃない。無理して只の友達で居続けようとするから、おかしなことになるんだ。
そんなこと無理なのに。――多分、ルルーシュにも、僕にも。
未だ無言のルルーシュへじりじりと距離を詰めていきながら、僕は言った。
「別に返事はしなくていいよ。いつか聞かせてもらえるならそれでもいいけど、君が僕を好きなのは言わなくても解っているから。……だから、君は」
「――――」
「これから僕がすることについて、一切拒否しないでいてくれればいい」
いいや。やっちゃおう。ルルーシュだから大丈夫だ。
こういう信頼のされ方はルルーシュにとっては不本意の極みでしかないかもしれないけど、ルルーシュは怒っても嫌がっても最後には受け入れてくれる。……うん、これは絶対。
だって、ルルーシュは絶対に僕のことが好きだ。この反応見れば解るよ。だから拒絶しない。今は戸惑ってても、最後には必ず僕を受け入れる。
ルルーシュは自分でも気付いてないかもしれないし、こういうこと考える僕も大概かもしれないけど、ルルーシュの愛情には男女の垣根が無いから。
それに、君にとって、僕は特別だろう?
言っとくけど、僕にとっても特別だ。僕はストレートだから、こんなこと考えるのだって君に対してだけだ。
断るなよ、ルルーシュ。僕は君に乱暴したりしない。出来ることなら優しくしたいんだから。……解っているよな?
ああそれと、僕は、可愛くない君を可愛くするための良い方法を思いついたよ。――たった今。
「ルルーシュ、僕、決めたよ」
僕は、全身を固く縮めているルルーシュの肩に手を置いて体重を掛ける。そして、ゆっくりと引き倒し、ベッドに寝かせた。
「君を今から、僕のものにする。反論は受け付けない。……いいね?」
「……!? ……!!?」
横たわったルルーシュが、ビクッ! と上体を震わせた。相当激しい混乱に叩き落されたらしく、百面相になりながらあたふたとベッドに肘を付き、僕から距離を置こうと伸び上がる。
言ったろ? 拒否するなって。
逃がさないよ、ルルーシュ。
「君の彼女には悪いけど、きっとその彼女よりも僕の方がよっぽど君のことをよく知ってるし、君のことが好きだ。だからルルーシュ。君にも悪いけど、彼女とのことはすっぱりと諦めて、僕にしろ」
言うなり僕はルルーシュを押し倒し、浅く短い呼吸ばかり漏らしているその唇をぴったりと塞いだ。
……正真正銘、今度こそ本当のキスだ。
「―――っ!? んんんっ!!?」
途端、可哀相なくらい全身を竦ませていたルルーシュが、組み敷いた僕の下で我に返ったように大暴れし始める。
……けど、もう遅いよ、ルルーシュ。
僕はやめるつもりなんて更々無い。そして君も、拒否出来ない。
断言してもいい。君は絶対、僕に落ちる。
何故かというと、本気を出した僕にルルーシュは結局逆らえないからだ。そしてそれは、昔から僕とルルーシュにとってお決まりのパターンだった。
僕は普段から、ルルーシュに負けてるんじゃない。負けてやってるんだ。いい意味で。
「やっ……! やめっ! やめろスザクっ!!」
「嫌だ」
唇を解放した瞬間、身を捩って怯え切ったように訴えてくるルルーシュに、僕は即答した。
今更やめるとか後に引くとか、そんな選択肢なんか最初から無いよ。
「君が欲しい。だから手に入れる。もう決めたんだ」
聞いているのかいないのか、最早逃げることしか考えていなさそうなルルーシュは、自制を完全に失ってじたばたと暴れている。
僕は瞳に涙を浮かべながらガクガクと震え、往生際悪くのたうちながらも、何とかして僕から逃れようとしているルルーシュを無理やり押さえつけ、わざと耳元で囁いた。
「愛してる」
「―――!!」
その刹那、ルルーシュが弾かれたように顔を上げてきた。
綺麗な涙が一粒、ぽろっと眦から零れ落ちる。
僕は流れた筋を辿るように舌を巡らせ、ちゅっ、と音を立てながらルルーシュの目元に吸い付いた。本当は塩辛く感じられるはずのルルーシュの涙は、僕にとっては寧ろ甘露だ。……どうしようもないほどに、甘い。
ルルーシュは首根っこを掴まれた猫みたいに縮み上がり、全く動けずにいる。そんなルルーシュを見て、僕は思った。
――多分、ルルーシュはすごく快楽に弱い。気持ち良いことに対する耐性が、物凄く低い。
何故か、そんな気がする。
さっき薬を飲ませた時にも思ったけど、そういえばルルーシュって、案外スキンシップ好きだったりするもんな……。
そういえば、彼女とはどこまでいってたんだろう。キスだけであんな風になるくらいだから、きっとそこまで進んだ関係ではないと思うけど。
彼女がいる?――で? だから何だ。
『僕らもう十七歳なんだから、そういうことがあったって、普通だろ』
僕は馬鹿だ。どうしてあんなことを許したりしたんだろう。
大体、ルルーシュはちょっと流され易すぎるよ。さっきも思ったことだけど、まさかこうやって誰かから迫られるたびに、すぐ大人しくなって受け入れてばかりいるんじゃないだろうな。
なんだろう……。そう考えると、自分でも少し異常だと思うくらい腹が立つ……。
そこで、僕は更に追い討ちをかけてやることにした。
「君がそうやって泣いているのも、僕を殴らないのも、君にとって僕が特別で大切な存在だからなんだって、思っていいよな?」
「…………」
「答えて? ルルーシュ」
僕は、とびっきり優しく聞こえる声を選んでルルーシュの耳元へと吹き込む。
鼻先を近づけたルルーシュの首筋から、またクラクラするようなとてもいい匂いがした。この髪から香っているんだろうか。それとも、何か変なフェロモンでも出てるのか?
そうだよ。ルルーシュの、この香りもいけない。だって、あまりにもいい匂いだ。
これがまた僕の理性を飛ばして、たちまちおかしくしてしまうんだから。
「ねえ……早く。……お願いだ」
僕はふわふわと揮発するソープの香りにも似たルルーシュの体臭に陶酔しながら、わざと吐息がかかるように囁きを繰り返した。
すると、ルルーシュの細い顎が堪え切れないように、ひくん、と動く。
そう。正気には戻らなくていいから。
それから、余計なことも一切考えなくていい。……ただ、黙って僕を受け入れてくれ。
「……す、ざく……」
しばらくして、ようやくか細い声が返された。
動きを止めたルルーシュは大きなアーモンド型の瞳をうるうるさせていて、追い詰められた小動物みたいにカタカタと小刻みに震えていて。
やばい。……すっごい可愛い。それに、なんか物凄く嗜虐心そそられる。
気のせいかな。でも、気のせいってことにしておかないと、さすがにちょっとまずいかも。
……まあいいや。
こうなったら、絶対落としてやる。誑かして蕩かせて、絶対に感じさせてやる。
僕も男だ。相手も男だろうが何だろうが、もう関係ない――。
僕はそう思うなり、ルルーシュの唇に吸い付いて顎を捕らえ、口を開けさせるために下へ引く。くん、と顎が下がったと同時にきつく引き結ばれていた唇がほどけ、ルルーシュがうろたえたような吐息を漏らした。
僕はその吐息ごと飲み込むように深く舌を差込み、熱い口腔内で逃げ惑うルルーシュの舌を捕らえる。
最初はゆるく、徐々にきつく舌を絡めていけば、ルルーシュは息を詰まらせながらポロポロと涙を零した。
「こういう時には、目を閉じるんだよ。ルルーシュ」
「や……」
「いやだ、じゃないだろ。目は閉じてろ」
「……っう」
低い声で命令すると、ルルーシュはぎゅっと目を瞑った。
普段なら、僕は絶対、ルルーシュに向かってここまであからさまな命令口調は使わない。ルルーシュだって、僕がもしこんな言い方なんかしようものなら、まず従ったりはしないだろう。
けれど、全く免疫の無いことをされているせいか、ルルーシュはいつもの尊大な態度もどこへやら、信じられないほど大人しくて従順だった。
いつもこうだったらどんなにいいか。……でも、そんな都合のいいルルーシュはルルーシュじゃないようにも思える。
きっと僕だって、それじゃつまらないと思うのかもしれないな。
……ああ、そうだね。女の人が行為の時だけちょっと下品でいてくれればいいのと同じように、ルルーシュもこういう時だけ素直になってくれればいい。
思った通りだ。――ますます可愛い。
99% (スザク幼少)
ゼロバレ前のスザク独白。
幼少スザルル回想。
大分前に書いてから、ずっとUPし損ねてたものです。  99%
99%
昔から、真っ白な雪道があれば、まずそこを踏み荒らすような子供だった。
理由はわからない。もしかすると、ただ面白かったからなのかもしれない。
僕は、昔からそういう子供だった。
勿論、僕はそんな嘗ての自分を恥じているし、生まれ持ったこの本性ほど疎ましいものは無いとさえ思っている。
「俺」がこんな醜い人間でさえなければ、こんな悲劇が起こる事は無かった筈だ。だから、突きつけられたこの現実は、紛れも無く「俺」自身の業なんだろう。
優しくならなきゃ。いつだってそう願ってる。
あの時、それまでの「俺」という呼び方から「僕」に変えようと思ったのも、今思えば極々自然な流れだったのかもしれない。
でも何故だろう。その時目の前に居た彼を模倣しようとでも思ったんだろうか? 無意識のうちに縋ってしまったんだろうか、僕は?
多分、そうなんだろうな。
俺は「俺」のままでいてはいけない。「僕」になれるよう、自分自身を変えていかなければ。……そう思った事だけは、事実だから。
全く価値の無い人殺しとしての生を生きる罪人の僕には、人として正しい生き方を選ぶ事など、もう出来ない。
だけど僕は、7年前に止まったままの時の中で、今もこうして生きてしまっている。
僕みたいな人間は、本来なら、もう生きていてはいけないんだろう。
だからせめて、正しい死に方を選ぶ事で償いたいんだ。
自殺なんて間違った方法を選ぶつもりはないけれど、どうせ死ぬなら、僕は正義に殉じて死にたい。
それこそが僕にとってふさわしい罰で、今の僕に出来る精一杯の、唯一の償いだと思うから。
勿論、死んだ方がいい人間がいるなんて、僕は思わない。生まれてきた時から悪人だった人間も。
でも、生まれてこない方が良かった人間なら、もしかするといるのかもしれない。たまに、そんな風に思う時がある。
どうすればいい? どうすればいいのかわからないんだ。
生きるという事がどういう事なのか、僕にはよく解らない。
僕に必要なのが人としての価値なんかじゃなく、ルールでしかない事が解ってしまった以上、それを決めたり求めたりする権利も、もう僕には無いと思うから。
ただ、これ以上人が死ぬ事の無い世界を創る責任が、僕にはある。
自分が引き起こした、この悲劇を収める責任が。……だから僕は、まだ死ねない。
僕は一生自分を許せないし、許す訳にはいかない。それが人殺しの生き方だから、個人である事はもう放棄しようと決めた。
いっそ機械のようになってしまえたら。心の無い人形のように扱ってもらえたら。
でもそれは、命令されなければ何も解らない人形であってはいけないんだ。
死に方ならとてもよく解るのに、生き方だけが選べない僕にはマニュアルが必要なんだろう。
今の僕は、命令されていなければ生きていけない人間だ。
だって、これが正しいと思っている僕の考えでさえ、結局は罪に足掻く醜い個人の考えでしかない。
間違ってるものは、正されなきゃいけない。
今の世界が平和になる為に必要なものは、正義に基づく規範だと思う。
だから、僕に必要なものは生きる権利なんかじゃなくて、義務と責任だけでいい。
それこそが、僕の求めるべきものだ。
でも、正しいって、一体どういうことを正しいっていうんだろう。……もし、間違ってしまったら?
ただ、これだけは確かだと思う事なら、僕にもある。
少しでも気を抜けばすぐに力を行使しようとする人殺しの「俺」を、「僕」は生きている限りずっと、戒めておかなきゃいけない。それだけは確かだ。……だから僕は、軍にいる。
一時の感情に任せて行動する事は、人として間違った結果しか生み出さない。例えその感情の裏に、如何なる理由があろうとも。
怒っちゃいけないし、憎んじゃいけないんだ。「生きて」いたいなら。
ましてや、戦うことや争うことを肯定するなんて……。
心無き力は只の暴力だというけれど、目的の為に手段を選ばず力を行使するというならば、例えそこにどんな理由や矜持があろうとも、それは紛れもない悪だ。
肯定出来ない。絶対に駄目だ。
何故なら、僕がそれを自分に許してしまった時から、力という名の手段を求めて刃を抜いたその時から、全ての悲劇は始まってしまったのだから。
間違った手段で得た結果は、やがて途方も無く大きな罪として返ってくる。
巻き込まれるのが自分だけならいい。でも、齎される結果は、その被害を被るのは、絶対に自分だけではない。
……それが、現実だ。
だからゼロ。
お前みたいな奴は邪魔なんだ。
お前のような奴は、世界に必要ないんだ。
君のやり方は、間違っている。嘗ての僕と同じように。
――だから、僕が。
俺が。
君を、終わらせるよ。
遠く広がる雪原は、僕の原初の風景のうちの一つだった。
匂い立つような緑の雑木林も、長く続く階段も、そこを汗まみれになって登ってくる、幼く美しい兄妹の姿も。
それ以前の記憶は、不思議とあまり無い。
毎日の稽古で叩き合う竹刀の感触以外は、きっと、どうでもいいような事ばかりだったせいだろう。
ねえ、ルルーシュ。君は覚えているかな。あの夏の日を。頭の良い君の事だから、きっと忘れる事なんか無いだろうけど。
決して良い事ばかりではなかったし、僕にとっては最後に赤く染まってしまった記憶でもあるけれど、僕も一応、まだちゃんと覚えている。
でもどうしてだろう。
一つ残らずあの頃の事を覚えておきたいと思っているのに、日々、掌から零れ落ちるように色褪せていくのは……。
あの頃は良かった。いつか君たちと、そんな風に笑い合えたらと思った事もあったのに。
たとえ、そんないつかが決して訪れはしない事を知っていても。
それでも僕は忘れない。――忘れられないんだ。
あの日に見た君の笑顔と、まるで灰色の空を舞うひとひらの雪のように、切なく眩しいまでの、尊い優しさを。
ブリタニアにも、雪は降るのだろうか。
そんな疑問を口にしてみれば、年齢に見合わず博識だった黒髪の少年は当たり前だと言いながら笑っていた。
その年の冬は殊更に寒くて、珍しく雪まで積もっていたから、僕は屋敷の離れと言えば聞こえがいいだけの土倉で暮らす兄妹が、たった一晩の間に凍え死んでしまわないだろうかと随分気を揉んだものだった。
車椅子無しでは移動出来ない彼の妹は、ひ弱にしか見えない兄と同じく体が弱くて。
だからその日は彼と――ルルーシュと二人きりで、買い物に行った。
「おいルルーシュ、大丈夫か?」
「別に、これくらい……平気、だっ!」
見渡す限りの雪原。一面の白。
ちらちらと粉雪の舞う雪原の真ん中をショートカットすれば、目的の店への近道になる。
そう言ってやれば、出来る限り人目を避けたがる事が常なルルーシュは、しぶしぶながらも僕の後を付いて来た。
白く煙る息を荒く吐き出しながら、足場の悪さにモタモタと歩を進めている彼へと呼びかければ、いつも通りの強気な答えが返ってくる。
「そんなトコ歩いてるからだろ? うっかりしてたらコケるぞ」
せっかく歩きやすいように、わざわざ雪をこいで道を作ってやってるのに。
僕はそう思いながら、柔らかい新雪が薄く積もった浅い道を選んで器用に歩いていく。
強がってはいるけれど、膝丈にまで届く雪の深さに足を取られて上手く歩けないんだろう。中途半端に作られたでこぼこ道の方が雪の深い場所と浅い場所があってかえって歩きにくいのに、ルルーシュは何故か僕が作る新しい道ではなく、わざと獣道のような場所ばかり選んで歩いていた。
「しょうがない奴だな。待っててやるから、早く来いよ!」
「うるさい! 別に待ってなんかいなくていいから、さっさと先に行けばいいだろ!」
慣れない足取りで歩くルルーシュは、ひっくり返りそうになりながら憎まれ口を叩いている。離れた場所を歩いているせいか、少しだけ声が遠い。
遠目から見ていると、その様はまるで酔っ払いの千鳥足のようだ。
「買い物に行くのお前なのに、俺が先に店着いたって意味ないだろ? いちいちそんな遠回りなんかしてないでこっち歩けばいいじゃん。なんでこっち来ないんだよ?」
ぐっと言葉を詰まらせたルルーシュは決まり悪そうに黙り込んだ後、一瞬言葉を返す事を躊躇うように瞼を伏せた。
「だって、そんなの……」
「なんだよ?」
「綺麗なものは、綺麗なままでいて欲しいって思ったからに決まってるだろ!」
心持ち頬を膨らませながら、むっとしたように言い返してくる姿は気丈というか、頑固というか。
夏に海に行った時の事を思い出し、何となく笑いが漏れる。釣りの時には「網を使った方が合理的」とか散々風情の無い事を言っていたくせに、この不器用な友人は、自分が不便な思いをしてまでも、新しく雪の積もった綺麗な場所を踏み荒らしたくないと言うのだろうか。
「バカだな」
「なんだと!? バカとはなんだ!」
つい反射的に貶してしまったけれど、少し離れた所を怒ったようにざくざくと歩くルルーシュの言葉は、なんとなく面映くて、微笑ましくて。
けれど、それと同時に、何かどうしようもなく、そして途方も無いものが心の奥底で僅かにざわめく。
自分でも訳の分からないそんな気持ちを、その時の僕は、特に意識もしないまま飲み込むしかなかった。
元々は近道の筈だったのに、足の遅いルルーシュを待つ度に立ち止まってばかりいた所為か、雪原を抜けるまでの時間は途方も無く長く感じられた。
けれど、ようやく追いついてきたルルーシュに向かって笑いかけてやれば、彼はいかにも得意気な顔つきで誇らしそうに笑っている。
視界を埋め尽くす雪に雲間から差し込む光が反射して、その時の世界はまるで、真っ白な光だけで作られているかのようだった。
光の中で、ルルーシュが笑う。
凍った空気の欠片にキラキラと彩られながら、どこまでも白く。美しく。
その彼が、かの帝国に捨てられた「要らない子供」だったなんて、一体誰に想像出来たというのだろうか。
僕は今でも、そう思っている。
99%黒。残る確立は、僅か1%
……それでも、僕は信じていたい。
雪のひとひらなんて、触れれば容易く溶けてしまうのだと解っているのに。
君の本質を羨ましいだなんて、思いもしなかったあの頃。
幼いがゆえに感じていた理由も根拠も解らない好意と、まるで、伸ばした指先から何か大切なものがすり抜けていくような、あの感じ。
今なら解る。それは「羨望」
自分には決して届かない、触れられないものに対する「憧憬」
「綺麗なものは、綺麗なままで」
だからこそ。
僕は、当り前のようにそう言った君を、守る自分でいたかった。
夏風邪のルルーシュ 3
けほ、と小さな咳の音が響いた。
と、同時に、ルルーシュの瞼がゆうるりと見開かれていく。
「あ、起きた?」
「…………」
現れた菫色は、天井を向いたまま心許なく揺れていた。まだ熱に浮かされているせいか潤んではいるけれど、呼吸の方は少し寝たこともあってか、さっきより幾分落ち着いている。
「大丈夫か?」
椅子に座ったまま屈んだ僕は、足元のバスケットからミネラルウォーターのペットボトルを取り出した。
「喉渇いてるだろ。下から持ってきたんだ」
まだぼんやりしているルルーシュの目前でボトルをかざしてやれば、視線をさ迷わせていたルルーシュの瞳がボトルを捉えてから僕の方へと向けられる。
キャップを空けて「飲める?」と差し出してやると、ルルーシュはこくんと素直に頷き、布団の中から気だるげに手を伸ばしてボトルを受け取った。
「薬もあるから」
ベッドからのろのろと起き上がったルルーシュは、ごくごくと喉を鳴らしながら水を飲んでいる。よっぽど喉が渇いていたのだろう。みるみるうちにボトルの中身が少なくなっていく。
常の彼らしくもなく、今にもえずきそうな勢い。僕が大丈夫かなぁ、と見守っていると、ちょうどボトルの半分あたりまで一気に空けたルルーシュは、案の定口を離すなり「ぷはっ!」と息を切らしていた。
「ちょっとルルーシュ。慌てて飲まなくても、水は逃げないよ?」
笑いながら言った僕に、はぁ、と重く息をついたルルーシュは、濡れた唇を手の甲で拭いながらようやく顔を向けてくる。
「お前……まだ居たのか」
まだ居たのかって……。居たに決まってるだろう。
ばつが悪そうなルルーシュに向かって、僕は肩を竦めながら言った。
「そりゃあね。だって、このまま帰るわけにはいかないじゃないか」
拭ってもまだ湿り気の残る口元や手の甲が気にかかるらしく、ルルーシュは何かを探すように緩慢な動作で辺りを見回している。
僕は「あ、タオル」と言いかけてから、テーブルにティッシュの箱が置かれていたことを思い出し、反射的にそこから一枚抜き取ってルルーシュに渡した。
「あ、ああ……。悪い」
受け取ったティッシュで口元を拭い、手の甲をぽんぽんと叩いていたルルーシュは、くしゃりと丸めたそれをどこへやるともなく握り締めている。
ゴミ箱、ちょっと遠いな。
そう思うなり、僕は無言でルルーシュへと手を差し出していた。
「ちょうだい」
「えっ?」
「それ」
「でも――」
「いいから」
僕はまごついているルルーシュから使用済みのティッシュを奪い取り、後方へと振り返ってゴミ箱に放った。
固く丸めたそれは、綺麗な放物線を描きながらシュートインだ。
「相変わらず器用だな」
驚いたルルーシュは目を白黒させている。君はまあ、こういうのは下手そうだよね――とは、さすがに口には出せないので、僕は正直に答える代わりに軽く笑っておく。
体を起こしたせいか、ルルーシュの額に貼ってあった冷却シートの端が少しめくれかけていた。気付いた僕が貼り直してやろうと手を伸ばしたところで、ルルーシュは何故か遮ってくる。
「ルルーシュ?」
「後は自分でやるから、お前はそろそろ帰れ」
ルルーシュはそう言いながら、自分で額のシートを貼り直している。
まだ熱あるくせして何言ってるんだか。またいつもの強がりかと思ってルルーシュを見ていると、ルルーシュは額を押さえたまま「明日仕事だろ」と素っ気無く言い放った。
「無理だよ。だって君、まだそんな状態なのに」
「俺はもう大丈夫だ」
「…………」
ああまた……。はっきり言って根拠ゼロだよ。
どこが大丈夫なんだか、と思いながらも僕は黙った。そうやって、いつもやせ我慢ばっかり。まるで弱っているところを見せたがらない猫みたいだ。
僕が強引にルルーシュの手首を掴んで引き寄せると、ルルーシュは口を小さく「あ」の形にしながら非難がましい目つきで僕を睨んだ。
掴んだ手首からルルーシュの体温が伝わってくる。――まだ、かなり熱い。
「あっ……」
汗で粘着力の落ちたシートが再び剥がれそうになり、押さえようとしたルルーシュが一瞬手を引きかける。
でも、僕は離さない。めくれてきたシートの端を代わりにさっと押さえてやれば、ルルーシュは拒むだけ無駄だと諦めたのか、今度は大人しく目を閉じてされるがままになっていた。
「それ取り替える前に、まず薬飲もうか」
手首を離してやると、ルルーシュは戸惑いを隠し切れない表情のままおずおずと腕を引き、僕に掴まれていた部分を押さえながらこっちを見つめている。
まだ、決して納得し切れてはいないようだ。
「ほら、飲んで」
僕は構わず薬のシートからぷつん、ぷつんと二錠取り出し、広げたルルーシュの掌へと乗せてやった。
薬嫌いかどうかはわからないけれど、ルルーシュは受け取った薬をすぐに飲もうとはせず、掌に落ちた白い錠剤をほんの少しだけ見つめてから拳を作り、ほどなくしてまた僕へと尋ねてくる。
「だから、お前仕事は? 明日もあるんだろ?」
「言い忘れてたけど、実は明日休みなんだ」
「休み?」
「そう。メディカルチェックでね。明日までっていうか、検査結果が出るまでなんだけど」
ルルーシュは不審そうに眉を寄せている。というより、いっそあからさまなほど露骨に顔を曇らせた。
――ナリタでのことは、ルルーシュには言えない。
思い出すなり心の壁が分厚く目の前に立ちはだかるのを他人事のように意識しながら、僕は凝視してくるルルーシュから目を逸らした。
すると、ルルーシュが急に改まったような声で「なあ」と呼びかけてくる。
「ん、何?」
「お前、もしかしてどこか悪いのか?」
「……え?」
僕は思わず「突っ込んできて欲しくない所にばかり突っ込んでくるんだから」とぼやきそうになった。
「そうじゃなくて、定期検査だよ」
軍のね、と続けながら、平静を装った僕はそ知らぬ顔をして明るく振舞っておく。
新しい冷却シートを取り出してフィルムを剥がし、受け取ろうとしたルルーシュの手を避けて「今貼ってるやつ剥がして」と指示すると、ルルーシュはこれもまた大人しく額のそれを剥がした。
ぺとり。
「――っ」
ルルーシュが、また冷たさに首を竦めて息を飲む。さっき寝ていた時は、瞼を痙攣させていただけだったけど。
「薬、飲んだ?」
まだルルーシュが握り締めたままなのを知っていながら僕はわざと訊く。すると、ルルーシュはむっと顔をしかめてから薬を口の中へと放り込み、水と一緒に流し込んだ。
唇から離れたボトルの水が、中でたぷん、と音を立てる。
「はい、キャップ」
短く告げて蓋を渡してやると、ルルーシュは一時困惑したように目を泳がせた。蓋を締めてからもボトルを持ったまま、どこに置こうかと枕元を見渡している。
「水、もういいならこっちに置いとくよ」
「…………」
僕が手を差し出すと、ルルーシュはだんまりしたままボトルを渡してきた。僕は「それも」と、剥がした後の冷却シートも指差し回収にかかる。
ルルーシュは面白くなさそうな面持ちのまま、指先で摘んでいたシートを僕の掌にぽとんと落とした。僕は受け取ったボトルをバスケットの中に落とし、剥がしたシートはティッシュと同じく手首のスナップを利かせてゴミ箱へと投げ入れる。
向き直ったそこには、不満も顕にむう、と唇をへの字に曲げているルルーシュがいた。
人の世話をすることはあっても、自分が世話されることには慣れてないって顔だな、これは。……まあ、僕は結構、君の面倒見てると思うけどね。
「ねえ、ルルーシュ」
「? なんだ」
「いつも思うんだけどさ」
「ん?」
「君、どうしてそういう顔するの?」
「……はぁ?」
ほら、そのポカンとした顔も。……って、まあ、この顔はそこまででもないか。
普段学校でつんと取り澄ましている時とは違って、僕と二人きりでいる時のルルーシュは、実はすごく表情が豊かだ。
どんなアングルから見ても、どんな表情の時でも、確かにルルーシュの造作はずば抜けて整ってはいる。別にいつも繕ってろって言いたいわけじゃないし、ルルーシュにとってはこれが普通なんだってことも、一応は解ってるつもりだ。
でも何故だろう。時々、とても残念な感じがするのは。
なまじっか造りが綺麗なだけに、そう思うのかな。――やっぱり君、ちょっとガサツだよ。
どうやら少しご機嫌斜めらしいその頬を、僕は冗談交じりにちょん、とつついてやった。
「何をする!」
「眉間に皺寄ってるぞ」
「……だから?」
「僕に看病されるのは嫌かい?」
「べ、別に、そういう訳じゃない……。ただ、俺は……」
「移すのが心配?」
どもるルルーシュにクスリと笑いながら尋ねてやれば、ん、と言葉を詰まらせたルルーシュはむっつりしながら口を噤んだ。
どう見ても図星だね、という言葉を、僕は喉の奥へと仕舞い込む。
……正直に言っちゃうと、そこで遠慮するくらいならもっと違う所でして欲しいかな。ねえ、ルルーシュ。
常々感じていたことだけど、ルルーシュは遠慮の仕方がすごく変だ。
人格自体ちょっと捻じれているから仕方ないと思うし、単なる感覚の相違と言ってしまえばそれまでなのかもしれないけど、僕はルルーシュからことごとくピントのズレた配慮をされることが多い。
そう。例えば、今みたいに。
というか、どうやら僕たち二人は感覚が真逆だ。僕にとって遠慮して欲しい時には全く遠慮してこないくせに、こうして遠慮して欲しくない時には遠慮する。……ほんとに、君ってややこしい奴だよ。
「それもあるが……定期検査って、具体的にどんなことを調べるんだ?」
「え?」
突然訊いてきたルルーシュに、そんなの決まってるじゃないか、と返しかけた僕はなんとなく口ごもった。
どうしてそんなことを訊くんだろう。具体的にって、何?
――けど、僕がそう思う時っていうのは、大抵相手に知られたくないことがある時なんだよな。
「本当に、どこか具合が悪いとか、そういうことは無いのか?」
ルルーシュはぼそぼそと聞き取りづらい声で尚も尋ねてくる。
やけに真剣な顔で訊いてくるなぁ。どうしたんだろう?
「具合が悪いのは君だろ? 僕はなんともないから、変な心配するなよ」
なるべくあっさりした口調を選んで言ってやれば、ルルーシュは物言いたげでありながらも一応黙った。
「それならいいが……」
ふっと目線を下げたルルーシュが、布団の上で組んだ自分の手を見ながら肩を落としている。
なんだよ、もう。いじらしいなぁ……。
自分の具合が悪い時にまで僕のことを本気で気遣っているらしいルルーシュの様子に、つい苦笑が漏れてしまう。
本来なら、男が同性の友達に心配されたり気遣われたり、あれこれ過剰に世話を焼かれるのって鬱陶しいことでしかない筈なんだけど、ことルルーシュを相手にしている時にのみ、僕のそういった基準は若干の誤差修正を強いられる。
それは一言で言ってしまえば、ルルーシュがルルーシュだからだ。
身内に対してハッキリと過保護で甘いところのあるルルーシュは、特にそういう傾向が強い。そんなルルーシュからすれば、修正前の僕の感覚は「個人主義」に分類されてしまう訳だけど。――でも多分、僕の感覚は普通だ。
だからこういう時、僕はやっぱり複雑な気分になるし、考えすぎとは思いつつ警戒もしてしまう。
……ルルーシュ、気持ちは有難いけど、君、僕を抱え込んでるような気になってやしないか?
勿論これは只の勘でしかないけど、ルルーシュを相手にしてる時の僕の勘って、あまり外れたことは無いような気がする。
それにしても、つくづくルルーシュは「相手イコール自分」になっちゃう奴なんだな。愛情深いというより、きっと情が深いんだろう。
でも、いつもつんけんした態度ばかり取ってくるくせに、やっぱりこういうところは変わってないんだよな、と思うと、僕はその度にいつもルルーシュに絆されてしまう。
とてもじゃないけど、ルルーシュ相手にすげない態度なんか取れないよ。
本当は、人が僕のことを気にかける必要なんて無いと思うのに……。たとえ、それが友達であっても。
それなのに、どこか捨て置けないほどの可愛らしさやいじらしさに、僕は結局負けてしまう。とにかくこう、根が優しいっていうか、健気っていうか……。
「心配しすぎだよ、ルルーシュ。僕のことより、今は自分の体調のこと考えなってば」
自然、声音も優しく甘いものになってしまって、僕はまるで女の子と話す時みたいにルルーシュと接してしまっている自分自身に酷く戸惑うことになる。
けれど、言いながら、心配しすぎなのは僕の方だと少し思った。……ルルーシュが、ナリタでのあの出来事について知っている筈もないのに。
ナリタで僕は、父さんを見た。
錯乱してヴァリスを暴発させた僕の様子に、特派の人たちもびっくりしたようだ。
今回のメディカルチェックは通常の身体検査とは異なり、主にカウンセリングや心理テストを中心としたものになった。身体的なことではなく、心の方に問題があるのではないかと疑われたせいだ。
でもこれは、ルルーシュにだけは絶対に知られたくない。寧ろ、ルルーシュにだけは絶対知られる訳にいかなかった。
――だってこれは、僕にとって最大の秘密なんだから。
「なあ、スザク」
「ん?」
「お前、やっぱり今日は帰れ」
「…………」
僕はなんともないと言ったのに、ルルーシュは思いつめたような顔を向けてくる。……やっぱりね。引く訳ないか。
全くもう。言い出すと思った通りのことを言ってくるんだから。
「どうして?」
目を平たくした僕を見て一瞬はっとしていたルルーシュは、けれどすぐに真顔へと戻ってから言い募ってくる。
「どうしてって……どうしてじゃないだろ。宿題見てやるって話だったけど、それも出来そうに無いし……。それに、お前に移すのだけは絶対に御免だ。俺は、お前にそういった迷惑は、その――」
一言区切る合間ごとにちらちらと僕の様子を伺いながら、ルルーシュはいかにも言い辛そうにぽつぽつと話した。
どうしてそんな態度なんだろう?
と、台詞の裏にあるルルーシュの気持ちを察した僕もまたはっとなり、そして同時に気付く。
……あ、そうか。
気にしてるんだ。さっき僕が言ったこと。
「ルルーシュ」
「え?」
「僕が居たら、休めない?」
「いや、別に……」
「それとも、僕がここにいちゃ何かまずいことでもある?」
「いや、それも特に無いが――って、そうじゃない! まずいに決まってるだろ」
「何が?」
「何がって、お前な……」
疲れ切ったとも困っているともつかない顔をしたルルーシュは、気まずそうに僕から目を逸らしたまま、頻りに何かを訴えかけては唇を閉ざす。
その様子は、僕を後悔の渦へと巻き込むのに充分な威力を持っていた。
言わなきゃよかった。あんなこと。頼ってるとか、甘えてるとか……。だって、ルルーシュはこんなにもプライドが高いのに。
僕は昔から、腹を立てている時に上手く言葉を選ぶことが出来ない。行動だってそうだ。いつも思い浮かんだまま衝動的に口に出したり振舞ったりしては、こうして失敗する。
僕は自分のそういうところが大嫌いで、でも、直せない。本当は、もっと思慮深くありたいと思っているのに。
ルルーシュに捲くし立てた僕は、内心ひどく焦っていた。でも、なんでこんなに必死になっているんだろう?……自分でもよく解らない。
ただ、断られたらどうしよう。ルルーシュに拒絶されたら――。
僕の中は、その思いだけで一杯だった。さっきまでの余裕なんかとっくに吹き飛んでいる。……とにかく、不安でたまらない。
「だったらいいじゃない」
焦燥を隠してあっけらかんと言い放つ僕に、ルルーシュは呆れた声で「はぁ?」と漏らしてきた。
「あのな、そういう問題じゃ……」
「そういう問題なんだよ。だって――」
「……だって、何だ?」
「僕は迷惑じゃない。相手は君だ。そうだろ?」
「――――」
僕は、強引な理屈だと承知していながら駄目押ししてみる。それも、なるべく優しそうに見える笑顔付きで。
知ってる。ルルーシュは昔から、こんな風に僕から押されると弱いんだ。
いつもなら、大体これで負けてくれる。……ところが。
「――っ、駄目だ!」
ルルーシュは頑として首を縦に振ろうとしなかった。それどころか、まるで聞き分けの無い子供を見るような目つきで僕をじっと見据えている。
「ええ? どうして!?」
つい情けない声が出た。なんで今日に限って……。
「咲世子さんだって、夜中寝てなきゃ昼間は動けないだろ? 第一、君が早く良くならなきゃナナリーだって心配する!」
僕は次第に焦れてくる気持ちをなんとか抑えて更に言い立てた。
「それはそうだが……。でも、お前は――」
ルルーシュは矢継ぎ早に話す僕の勢いに困惑しているのだろう。若干たじろいでいて引き気味だ。
口ごもりつつもなかなか折れてくれないルルーシュを前に、僕は苛々しながら尚も押そうとしていた。
ここまでくると自分でも疑問に思えてくる。どうして僕はここまでムキになってるんだろう。別にいいじゃないか。ルルーシュが帰れって言ってるなら、それで――。
……いや、解ってる。
これは、ルルーシュの気持ち云々の問題じゃない。――僕が、帰りたくないんだ。
結局こうなるのか。そう思いながら、僕は自分自身に呆れたように嘆息した。要するに、また惑わされるんだ。こうやって。
薬が効き始めているとはいえ、澄んだルルーシュの菫色はまだ少し熱で潤んでいる。線の細い肩だって余計頼りなく見えるし、夜中になったらもっと具合悪くなることだってあるかもしれない。
複雑な事情を抱えているルルーシュは、そう簡単に病院に行ったりすることもないんだろう。だって、この辺は政庁とも近いから、病院には軍関係者の人間だってよく出入りしているんだし。
無理して気を使ってまで僕を帰そうとしているルルーシュを放っておくことなんか、やっぱり僕には出来ない。
さっきは色々ときついことも言ってしまったし、それに……。
「解っているだろ? ルルーシュ。僕相手に変な遠慮なんかしないでよ」
「スザク……」
しゅんとなったルルーシュは、正に触れなば落ちなんという風情だ。……よし。多分、あと一押し。
強がっていたって解る。ルルーシュは、本当は僕に帰って欲しいなんて思ってない。
「本当は君、ちょっと気にしてるんだろ。君が僕に頼ってるとか甘えてるとか言ったこと。だからこうやって遠慮しようとしてるんじゃないのか?」
「なっ! 俺は別に、そういうつもりじゃ……!」
ルルーシュは気色ばんでみせはしたものの、後ろめたそうに瞳を瞬かせながらへどもどと言い訳している。
やっぱりか、と思った僕は、黙ってルルーシュの鼻を摘んでやった。
「ぶっ、何をする!?」
「隠すなよ、ルルーシュ。君は僕に嘘なんかつけないよ」
「離せ、この馬鹿っ!」
ルルーシュは怒りながら僕の手をぺしんと叩き落とした。でも、そうやって誤魔化してみたって態度は正直なものだ。
それに、目は口ほどにものを言う。
実際口にすれば反発して余計言うことなんか聞かなくなるかもしれないとは思ったけど、こうして正直に自分の気持ちを言うことにしておいて正解だったと僕は思った。
ルルーシュは頭がいい反面、計算外のことやイレギュラーには極端に弱いから、下手に取り繕ったりするよりも、いっそズバリと本音を言い当ててやった方がよっぽど効果的なような気がしてたから。
「君は遠慮するところを間違ってるよ。こういう時はいいんだ」
「…………」
無言になったルルーシュが上目遣いで見上げてくる。それに僕がにっこり笑いかけてやると、ルルーシュはとうとうため息を漏らしたきり沈黙した。
これで、僕の勝ちだ。ルルーシュ風に言えば、チェック・メイト。
僕は一息つきながら、ルルーシュが眠っていた時に考えていたことについて猛省していた。
そうだよな。いくら頭が良くたって、ルルーシュが僕相手に隠しごとなんか出来るわけがないんだ。身内に対してはどこまでも甘い、このルルーシュが……。
一瞬でも疑いを抱こうとした僕が馬鹿だった。――と、僕が思った時、ルルーシュは。
「いや、やはりお前に移したくない。気持ちは有難いが今日は帰れ」
「………………………」
きっぱりした口調で、信じられないことを口にした。
どうして君ってそうなんだ? 忍耐力を総動員したとしても、これは、ちょっと、さすがに……。
――なんていうか、それはないんじゃないかな。
僕は何となく自分の目が据わっていくのを感じながら、椅子の横に置かれていたバスケットの中へとおもむろに手を突っ込んだ。
「ルルーシュ。そういえば君、まだ胃薬飲んでないだろ」
「胃薬?」
「うん。市販薬は刺激が強いから、胃薬と一緒に飲んだ方がいいんだ」
とか何とか言いながら、実はあんまりよく覚えてないんだけど。
僕はさっき開けたパッケージとは別の薬の箱を開封し、取り出した錠剤を手にしたまま立ち上がった。
「……? 何だ?」
急にベッドの上へと乗り上げてから腰掛けてきた僕を、ルルーシュは不思議そうな顔をして見上げてくる。
「どうした? スザク」
「うん? いや、別になんでもないけど」
僕は至近距離からまじまじとルルーシュを観察していた。間近で顔を覗き込まれたルルーシュが、困惑したようにじり、と腰を引く。
気付けば僕は、そんなルルーシュを更に追い詰めるかのように、無意識にルルーシュとの距離を詰めていた。
「おい……?」
「ん、何?」
「なんだ、これは?」
「うん。何だろうね?」
僕は、これもほとんど無意識のうちにルルーシュの体の両側を腕でホールドする。ベッドに座っているルルーシュもこれはさすがにおかしいと思ったらしく、どこか怯えたような顔をしながら尋ねてきた。
「お前……。何だろう、じゃないだろ……」
「そう?」
「ふざけてるのか?」
「さあ。どう思う?」
「…………」
そして、僕はというと。
ルルーシュの反応を余所に「逃げられないよね、これなら」と、頭のどこかで冷静に考えていた。
視点が合わないほど近くから見つめていると、アメジストのように光る綺麗な紫色の瞳がぱちぱちと瞬く。宝石っていうより、なんだか飴玉みたいだ。
――うん。とりあえず、大丈夫そう。
「ルルーシュさ、彼女いるよね?」
「はぁ?」
真正面で話しているせいで僕の吐息がかかったらしく、ルルーシュは一度だけ固く閉じた瞼を大きく見開いた。
「か、彼女……?」
「うん。いるだろ? この間いるって言ってたじゃないか」
「……?」
記憶検索中なのか、それとも言ったことを覚えていないんだろうか。まあ、ルルーシュに限ってそれはないか。
……どっちでもいいけど。
「安心して、ルルーシュ。これは、浮気には入らないから」
「は?」
ルルーシュにそう言い置きながら、僕はルルーシュの口ではなく、自分の口の中へと錠剤を放り込む。
「おい、お前何して……」
僕の手が口へと運ばれる所をつぶさに見ていたルルーシュが、驚いたように僕の目を見る。
弾かれたように顔を上げたその瞬間を、僕は狙った。
「―――っ!?」
喋りかけていたルルーシュの声は、僕の口腔へと吸い込まれて消えた。
顎を捕らえて重ねた唇を深くしながら、僕は心の中で呟く。
そう。簡単なことだ。
……移すのがどうしても嫌だっていうんなら、もう、移ること確定にしてしまえばいいんだろう?
夏風邪のルルーシュ 2
氷の入った枕と冷却シート。着替えに濡れタオルを二枚。
スポーツ飲料にミネラルウォーター。それから薬もちゃんと用意した。
きっと沢山汗をかくだろうから、念のためにバスタオルを一枚と、換えのシーツも一枚。……あと、洗面器。
さっき胸をさすっていたから、もしかしたら吐き気も少しあるのかもしれないし。
とりあえずこれでいいかな、と荷物をまとめた僕は、バスケットの中身を一つ一つ確認しながらルルーシュの部屋へと続く階段をゆっくりと上っていく。
汗、かいているといいけど。熱を下げるためには発汗させなきゃいけないから、まずは水分を沢山摂らせた方がいい。
……でも、飲めるだろうか。ルルーシュまだ起きてるかな。
とは言っても、寝ていなきゃ駄目なのも事実なんだけど。
僕は少し反省していた。さっきはちょっと言い過ぎた。本当に具合が悪そうだったのに。
人は心配すると怒るって、本当だったんだな。
ルルーシュが何を差し置いてもナナリーのことを最優先に考えるのは、昔からお決まりのパターンだ。いつもそれで無理ばかりして、自分のことを全て棚上げにしてでも常に妹のことばかり考えて。
彼らの境遇を思えば、それも無理からぬことなのかもしれない。ただでさえ、たった二人きりの兄妹だ。
――でも、と僕は敢えて思う。
何かと不安定なルルーシュを陰日向となって支えているのは、本当はナナリーの方なんじゃないのかと。
昔は違っていたけど、今のナナリーは、体のことさえ無ければルルーシュと離れて暮らすことだって出来るのかもしれない。
離れたが最後、生きられなくなるのはルルーシュだ。
だから、僕の目にはこう映る。
本当はナナリーのためというよりも、ルルーシュが自分自身のために彼女を過保護にしているのだと。
ルルーシュにとってたった一人の肉親である妹が、決して彼自身から離れていこうとしないように――。
部屋に入ると、少しだけ空気が篭っていた。
僕はドアの横にあるエアーコンディショナーの換気スイッチを押してから、ベッドの方へと歩み寄る。
ルルーシュは苦しげに胸を上下させながら眠っていた。薄く開いた唇から漏れ出す息が、少しだけ荒い。
足元を見回した僕はちょっと考えてから、手持ちのバスケットをベッドサイドに置かれた椅子の横に置いた。
暑くて寝返りでも打ったんだろうか。ルルーシュを見ると、首元まで覆った筈の布団が乱れて肩が露出している。
肌蹴たシャツの襟ぐりからそっと手を差し入れると、ルルーシュの肌はうっすらと湿り気を帯びていた。
……良かった。汗かいてる。
ほっと一息ついた僕は、床に置いたバスケットの中から濡れタオルを取り出し、汗で貼りついたルルーシュの前髪をかき分けてから丁寧に額を拭った。掌で湿り気を軽く抑えてから冷却シートのフィルムを剥がし、落ちてくる髪を抑えながら額にぺとりと貼り付けてやる。
「……っ」
すると、ルルーシュの瞼がピクリと動いた。きっと冷たかったんだろう。
目を覚ますかと思ったけれど、ルルーシュの瞼は開かない。一度緩やかに息を吐き出したその後は、心地よさそうな顔ですうすうと穏やかな寝息を立てている。
水分も取らせたいし、熱だって計ってやりたい。それに、薬も飲ませなきゃ。
あれもこれもと忙しなく考える中、僕の手が唐突にはた、と止まった。
……放っておけとか言われたって、こんなにも頼りないのに出来るわけないじゃないか、そんなこと。
意地っ張りだし、頑固だし、全くもって目が離せないような面倒くさい性格してるくせして、いつも憎まれ口ばっかり叩くんだから。
時々、本気で腹が立つよ。ルルーシュ。
子供の頃から思ってたけど、ホント、君って可愛くないよな。ちょっとは素直になってくれ。いつもこうやって、何かと僕を巻き込んでは困らせてばかりいるくせに。
ルルーシュはあくどくなった。再会してからは特に。
真面目に来いと言っているのに、学校には全然来ないし。それも、来ている時にまで平然と授業をサボろうとする。
出てたら出てたで寝ているし、裏社会の賭けチェスなんて非合法のギャンブルには手を出すし。
不良の元皇族なんて、聞いたことがないよ。
しかも、逃げたと気付いた僕が追いかけてくると解っていてサボろうとするところが特にあくどい。
君、絶対に楽しんでるだろ。
生徒会の皆も、ルルーシュのことで何か困ったことがあったら、とりあえず僕に訊けばいいと思ってる。
言っておくけど、僕はルルーシュの友達ではあってもお世話係じゃない。幾ら幼馴染とはいえ、別に四六時中一緒にいるわけじゃないんだから、何かある度にルルーシュのことを僕に訊かれても困るよ。
……いや、悪いのは皆じゃない。ルルーシュだ。
大体、普段から出席日数少ないくせして、どうして学校来てる時にまで屋上で電話なんかかけているんだ? 一体、どこの誰と話してるんだよ?
それに、気になることもある。
出先から電話をかけてくる時、ルルーシュがその所在について話してくれたことは一度もない。
最近は特に、その秘密主義ぶりに拍車がかかってる。一体どこから電話をかけてきているんだろう? それに、昼も夜も出掛けているようだけど、君はいつもどこで何をやっている?
少なくとも、賭けチェスなんかじゃないよな。
だって、リヴァルから聞いたんだ。「最近付き合いが悪い」って――。
確かに、ルルーシュは僕に対して「一緒に授業をエスケープしよう」とは一言も言っていないし、面倒を見てくれと頼んできたことだって一度もない。
……そう。結局、巻き込まれることを自主的に選んでるのは、いつも僕だ。
選んでるんじゃなくて、本当は選ばされている。多分そう言った方が正しい。
ルルーシュはいつも僕を惑わせる。――今日だって、君は無意識に僕を頼ってた。
君は、本当は知っているんだ。どういう時にどうすれば僕が動くのかちゃんと知っていて、いつも好き放題に振舞ってから「後のことは任せた」みたいに頼ってくる。すごく勝手だ。
僕はその度に「あ、また!」って思って、そして何だかんだで君に従ってしまう。
不本意ながらも、必ず面倒を見てしまうんだ。まるで身に染み付いた習性みたいに。
別に、それが嫌って訳じゃない僕も大概だけど……君は魔性だよ。時折、僕を弄んでいるのかと思うことさえある。
ずるいよ、ルルーシュ。
僕は普通の友達でいたいのに、君はいつだってそうはさせてくれない。
自分が僕を頼ってるってことについては絶対認めないくせに、君は解っているんだ。君を放っておくことの出来ない僕の気持ちを。
そして振り回す。かき乱すんだ。いつも。
……やっぱり、君は僕に甘えてる。
どう考えても、遠まわしに構われたがっているとしか思えない。
今日だって――。
と、そこまで思いかけた僕は、それ以上考えるのをやめておいた。だって、こうして挙げ出したらきりが無いから。
はあっと大きなため息をついた僕は、力無く横たわるルルーシュをまんじりともせず見つめた。
無茶ばっかりするんだから。
この分だと、しばらくは目を覚ましそうに無いな……。だったら、首にも冷却シートを貼った方がいいか。
あ。でも、その前に氷枕を当ててやらなきゃ。熱、少しは下がったかな。
確かめるために触れたルルーシュの首へと目をやった僕は、ふと気付く。
……細いなぁ、ほんとに。ちょっと力を入れただけで折れてしまいそうだ。
口を開けば毒ばかり吐くくせに、眠っているルルーシュの顔は性格とは真逆と言ってもいいくらいにあどけなくて、どこか無防備で、いっそたおやかにさえ見えてきて。
なんだか、妙に保護欲を誘われてしまって本当に困る。
全く、顔が良いって得だよ。
性格はひねくれてるくせして、寝顔は可愛いなんてちょっと反則だ。
いつも思うことだけど、とにかく放っておけない。まるで世話の焼ける弟のような、それでいて、僕より年上なのに手のかかる兄のような……。
そして、時として母親のような愛情深さで接してくる、僕の大切な友達。
――それなのに、そんな君と一緒にいる時の僕は、本当はちょっとだけ複雑だ。
普段ひんやりと冷たいルルーシュの体温は、今は子供のように高くなっている。ルルーシュの首から手を離した僕は、持ち上げた後頭部を支えながら枕を引き抜き、持ってきた氷枕と入れ替えた。
「ん……」
ぐったりしたまま、ルルーシュが小さく呻く。
僕は長い睫が震えているさまを見下ろしながら、これは学園の女の子たちがこぞって騒ぎ立てるのも無理はないな、となんとなく思った。
ルルーシュは昔から並外れて人目を引く姿の良い子供ではあったけど、成長してからは容姿の良さにも磨きがかかって、とんでもない美人になっていた。
君にとっては、目立つのなんか困ることでしかない筈なのにね。
まるでビスクドールのように整ったルルーシュの寝顔を見下ろしながら、僕は思わず苦笑した。
……それにしても、可愛いなぁ。こうして静かに眠っていると、本当にお人形さんみたいだ。
君はもう、ずっとそうやって眠ってたら? その方が、僕もよっぽど安心出来るんだけど……。
引き上げた布団を肩の上まで被せてから椅子に腰掛けた僕は、心の中でルルーシュに語りかけながら思い出す。
かなり苛めていたなぁ、小さい頃は。何かというと、すぐ「男のくせに」って。
……ああ、さっきも言ってしまったか。
まあ、それは、子供の頃に言ったのとはまたちょっと違う理由で……つまりは、さっき僕が思ってたような理由なんだけど。
でも、決してそれだけじゃなくて――。
枕の中の氷がカラコロと音を立て、傾いたルルーシュの顔が僕の方へと向いてくる。
「う、ん……っ」
魘されているようなその声に、ルルーシュが目覚めたのかと思った僕はハッと我に返った。眉を寄せたルルーシュが、寝苦しそうに首を捩らせながらこくりと喉を鳴らしている。
喉が渇いているんだろうに、起きられないのか。
どうしようかな。本当は早く薬を飲ませた方がいいんだけど、せっかく眠っているのにわざわざ起こすのも可哀相な気がするし……。
目覚めるのを待つべきか、それとも薬を飲ませるために無理にでも起こすべきか。
そう思いながら何気なく室内を見回した僕の目に留まった物は、机の上に置かれたルルーシュのパソコンだった。
「――――」
僕は一体、何を考えている?
止まったまま動かない目を無理やりパソコンから引き剥がし、僕は安らかな寝息を立てているルルーシュへと視線を移し変えた。
邪気の欠片もない綺麗な寝顔。
すっと通った鼻梁に、抜けるような白い肌。ルルーシュは男だと解っているけど、僕はつい見とれてしまう。
同性だったとしても綺麗なものは綺麗だし、美人は美人だ。勿論、ルルーシュにそんなこと言おうものならこっぴどく怒られてしまうんだろうけど。
いっそ場違いなほどどうでもいいことを考えながら、僕はルルーシュを見つめていた。
不意に、チクリと胸が痛む。
『軍の助けは借りない!』
ついさっきルルーシュが叫んだ台詞が、耳の奥でまだ尾を引いていた。
やっぱり君は、僕が軍属でいることを嫌がっているんだよな。普段僕の前では口に出さないようにしてるってことも、僕は知っている。
君が今まであの国にされてきたことを思えば当然だろうけど、君は今でも、具合の悪さも忘れて飛び起きるほどにブリタニアを嫌ってて、憎んでいるんだろう。
それこそ、容易く口になんか出せないほどに強く、激しく。そして根深く。
僕の中で、つい数日前、ルルーシュに言われた言葉が蘇る。
『シズオカ工場か?』
借りていた数学のノートを返しに来た時、明日から出張だと言った僕にルルーシュが訊いてきた言葉だ。
どうして知っている? 僕はあの時そう思った。
剣の取れたルルーシュの寝顔をじっと見つめながら、僕は心の中でルルーシュに問いかける。
ルルーシュ。……君は、軍のことを調べているのか?
――何のために?
あのパソコンの中身を覗いてみれば、少しはわかるんだろうか。再会してから、昔よりもずっと秘密主義になった君の秘密が……。
「彼女を心配させちゃうよ、ルルーシュ」
頬にかかった艶やかな黒髪を掃い除けてやりながら「早く治さないとな」と心の中で呼びかけたところで、僕はまたも気付く。
緑色の、長い髪をしているらしい、ルルーシュの彼女。
そして、ナリタに現れた拘束衣の女。
その女の長い髪の色も、確か緑色だった、と――。
突然よぎった自分の考えに、僕はギクリと心臓を縮ませた。
まさかな。ありえない。僕は自分にそう言い聞かせながら、無理やり思考を断ち切るように目を閉じる。
……ルルーシュ、ごめんな。僕は、君に嘘を吐いている。
技術部所属だと言ったのは確かに嘘じゃないけれど、あのランスロットに乗っているのが本当は僕なんだと知ったら、君は一体どう思うだろうか。
君が秘密主義に徹しているのも、きっと僕のせいなんだろう。
僕に一線引かれている。君は、本当はそう思ってる。
僕は知っているんだ、ルルーシュ。
君が時々、酷く寂しそうな目で僕を見つめているってこと。
君は僕に気付かれていないと思ってるかもしれないけど……馬鹿だな、ルルーシュ。気付かないわけないだろう?
君は意地っ張りだから素っ気無く振舞っているけど、本当は、僕の存在が遠くなってしまったように思えて寂しいんじゃないのか?
昔の俺なら迷うことなく、何よりも誰よりも、まず友達の気持ちを優先しただろう。
だけど今の僕は、昔の俺と同じであっちゃいけない。個人的感情よりも、組織の論理を優先しなくちゃいけない。
――いや、そう出来る人間になっていなければならないんだ。
君は尋ねてこようとしないけど、敢えてその話題には触れないようにしてくれているけど、僕がどうして軍に入ったのか、本当は疑問に思っている。
もしかすると、裏切られたような気持ちにさえなっているのかもしれないな。
……でも、その理由について君に話してやることは、絶対に出来ない。
だから、たとえ君が僕に何か言えない秘密を隠しているのだとしても、僕にそれを責める権利は無いんだ。
だって、僕も君に対して、どうしても隠しておかなければならない秘密を抱えているんだから……。
ルルーシュ。
君が好きだよ。……大好きだ。
でも、遠慮がちな気持ちを隠しながら誘ってきては、僕がここへ来る度に喜ぶ君を見て、僕は少しだけ不安になる。
そして、苛々するんだ。七年前と全く同じように接してこようとする君に。
酷いよな。『俺』は。
こんなにも君のことが大好きなのに。別に、遠ざけたいなんて思ってる訳じゃないのに。
もう二度と、君に会うことは出来ないと思っていた。だから僕は、君との再会を果たしてから一つだけ心に決めたことがある。
今の僕が置かれている状況は、とても特殊だ。
僕を君と同じ学校に入学させてくれた人は、誰だと思う?
ユーフェミア皇女殿下なんだよ。――君の、腹違いの妹だ。
元々ただの一平卒でしかなかった僕の周りには、今や考えられないほど高位の人たちが集っている。……だから僕は、上を目指すよ。中からブリタニアを変えていくために。
そしていつかこの国を取り戻して、君と……君たち兄妹にとっても住みやすい、命を脅かされる危険のない平和な国にしていくんだ。
……僕は、いいんだ。
たとえ裏切り者と呼ばれても、人殺しだと罵られたとしても。――だって僕は、元々罪人だから。
だからね、ルルーシュ。
この願いが叶う日が、いつになるかは解らない。もしかしたら、僕や君が生きているうちには果たせない夢なのかもしれない。
それでも、見守っていて欲しい。
守るから。必ず。
いつかきっと、君たちが幸せに暮らしていける世界を僕が創るから。
だから、それまで待っていて欲しい。早まったことだけはしないでほしい。
ゼロなんかに惹かれたりしないで。危ないことには踏み切ろうとしないで。……どうか、思い切らないで。
頼むから、お願いだから、どうか大人しくしていてくれ。
――そして、絶対『こっち側』には来ないで欲しい。
『まさか。ナナリーを泣かせるようなことはしないよ』
ルルーシュ。
僕はその言葉、信じてもいいんだよな?
……信じているから。
だから、裏切らないで欲しい。絶対に。――僕の、この想いを。
FC2ブログに「スザルルバトン」があったので
やってみた。
スザルルサイトだけど「そういやこういうのに答えたことないなー」と思ったので、今更のようにスザルルのことを答えてみました。
……が、語りきれていないwww(っていうか、語り切れるわけ無かった……)
サイトといってもブログなので日記的なものはツイッターしか置いてないし、要るかなぁ、ブログって考え続けて結局置いてません。
バトンとか久しぶりに答えた気がする……。
ノマカプに対する回答もしてますので、苦手な方はご注意です。
夏風邪のルルーシュ 1
ゴホンと一回大きな咳が出た。
思わずクソ、と心の中で毒づく。
寒風吹きすさぶ真冬ならともかく、くそ暑い真夏のさなかに、この俺が風邪をひくなんて。
ああいいさ……認めよう。夏風邪は馬鹿がひくものだ。
俺は愚かだ。
ベッドでぐったりと横たわるその傍らには、今にも「んもう」と言い出しそうな顔をしたスザク。
「ルルーシュ、どうして黙ってたんだ?」
「お前だって解ってるだろ……」
思いっきり険しい顔で尋ねてくるのでそう答えてやれば、くっきりと刻まれた眉間の皺がますます深くなる。
「やせ我慢だな」
「うるさい……」
ナナリーと三人で夕食を楽しむ。そのプランだけはどうにか終了した。
代償の如く襲ってくる嘔吐感。食したものが胃袋の中でぐるぐると蠢き、せっかく自ら丹精込めて作り上げた料理を全てリバースしそうになっている。
それが、今の状態だ。
「四十度……」
俺の腋から引き抜いた体温計を一目見るなり、スザクが呆然と呟く。
「君、馬鹿だろ」
「うるさいと言っている……」
「具合が悪いなら悪いって、なんで言わなかった?」
「…………」
尋ねられた俺は、思わず口ごもった。
言えるわけないだろう。ナナリーが楽しみにしていたんだ。ナナリーが。
横になっている俺の枕元に体温計をそっと置いたスザクは、偉そうに腕組みしながら俺を見下ろしている。
責めるような目つきに詰問調。どう見ても臨戦態勢だ。
こいつにとやかく言われる義理は無いが、くそ真面目で口煩いスザクのこと。……おそらくこの後、説教が始まる。
「僕が気付かなかったら、どうするつもりだったんだ」
「…………」
やはり来たかと思いながら、俺はスザクから目を逸らした。
案の定、こいつは俺を問い詰めにかかるつもりだ。
「ルルーシュ」
あまりにしつこいので無視していると、スザクがじろっと睨んできた。
なんだその顔は。何か文句でもあるのか? なら、さっさと言えばいいだろう。
とはいえ、黙っていても埒が明かないのは目に見えている。
俺は渋々口を開いた。
「ナナリーに気付かれなければいい」
「またそれか」
「それ以外に何がある」
訥々と答える俺を見て、スザクはあからさまに嫌な顔をした。
はあっと吐き出されたのは、大きなため息。
おい……何なんだ。そのこれ見よがしな反応は。
「それって、僕が気を回さなかったらそのままだったってこと?」
「……そうだよ」
だから気付かれたくなかったのに。
そう思いながらも認めてやれば、スザクは一旦目を閉じてもう一度ため息をもらしてから、今度は心配そうな顔を向けてくる。
「気持ちはわかるけど、過保護すぎるのも良くないよ」
「過保護にした覚えはない」
「充分過保護だよ。君が倒れてちゃ意味ないだろ。またの機会にすることだって出来るのに……。せめてこういう時くらい、素直になったら?」
「…………」
俺に反論の余地は残されていない。
スザクに諭された俺は、とうとう気まずく黙り込んだ。
熱でいよいよ意識が朦朧としてきた頃、そろそろ限界だなと判じたスザクに無理やり部屋まで連行されてきたからでもある。
『僕とルルーシュはそろそろ部屋に戻るよ』
夕食後、突然そう言い出したスザクに『え?』と見やると、スザクは俺を無視して『宿題、教えてもらうって約束してるんだ。な、ルルーシュ』と嘯いた。
宿題を教えると約束してあったのは、確かに嘘ではないが……。
スザクはこっちに目配せしながら『それじゃ、おやすみナナリー』と言い置き、俺の方へと接近。にこにこしていた顔が近寄るにつれて、冷たく平たい目つきに変わっていく。
苛立ち紛れの仏頂面で見下ろされた挙句、がしっと腕を引っ掴まれ、抵抗しようと腕を引けばじろりと睨まれ……。
立ち上がらされた俺は、仕方なく諦めた。
――だって、そうするよりほか無いじゃないか。
こういう時のスザク相手に何を訴えたところで、どうせ無駄に終わる。
蛇に睨まれた蛙の如く、俺は不本意にも奴に従い、素直に『はい、おやすみなさい』と答えたナナリーの声をバックにそそくさとリビングから退散した。
スザクは俺に気を使ったんじゃない。ナナリーに気を使ったんだ。
俺の具合が悪いと気付かれたら、ナナリーを悲ませてしまうとわかっているから……。
スザクは絶対、俺の言うことなんかまともに聞きやしない。昔から……。こいつはそういう男だ。
「もういいだろ……」
辟易としながら、俺は荒い息を吐き出した。
本格的に具合が悪い。漏れる息はかなり熱く、普通に話しているだけなのに苦しかった。
でも、スザクは空気が読めないのか、それとも最初から読む気が無いのか「よくないよ」と即座に言い返してくる。
「いいからタオルを取ってきてくれ」
苛々しながらうざったそうに言い放つと、スザクは心底むっとしたように顔をしかめた。
「八つ当たりか? それは人にものを頼む態度じゃないな。僕は君の家来じゃないよ」
ぞんざいな言い方をされたのがよっぽど気に障ったらしい。スザクは常に無くきつい物言いで凄んでくる。
お前な……さっきから顔が怖いんだよ。
一応迷惑をかけている自覚はあるが、だからって絡んでくるのはよしてくれ。
そして、頼むから空気を読め。俺は本気で具合が悪いんだよ……。
「俺を部屋まで引っ張ってきたのはお前だろ……」
「本当に態度デカいな。反省してないだろ」
「何を反省する必要がある……?」
早々と諦めた俺は、とりあえず視界をシャットアウトした。部屋の照明でさえ刺激になって疲労感が増長されていく。
こいつが空気を読まないのはデフォルトだ。言うだけ時間と労力の無駄になる。――それにしても、なんという失態。まさかこいつから説教される羽目になるなんて……。
すると、スザクは突然何を思ったのか呆れ顔のまま椅子から立ち上がった。
「冷却材みたいなものはないの?」
目を閉じたままの俺を見て、さすがにこのままではまずいと思ったらしい。
濡れタオルよりアイスノン。確かにお前は正しいよ、スザク。
少しは聞き入れる気になったのかと、俺は安心した。――ところが。
「咲世子さんに訊けば……」
と、俺が言っているのに、スザクは完全に上の空だ。
お前はどこを見ている? 俺の話をちゃんと聞いているのか?……いや、明らかに聞いてないだろ。
つい今しがた思ったばかりのことは俺の気のせい、もとい只の勘違いでしかなかったのだと気付き、安心が落胆へと変わってこの胸を覆い尽くしていく。
スザクは「うーん」と唸りながら首を一巡りさせ、突然くるんと身を翻した。
「医務室に行けばあるかな。ちょっと行って貰ってくるよ」
「? 貰う……?」
貰うとは、一体誰からだ?
一方的に言い置いてからスタスタと歩いていくスザクの後ろ姿に、なんとなく嫌な予感を覚える。
――今、こいつはなんと言った? 医務室?
どう考えても学園内の施設ではない。そう気付いた俺はハッとして、慌ててスザクを呼び止めた。
「待て!」
引き止める俺に、スザクが「何?」と振り返る。
言うや否やドアを目指して一直線か。一体どうなってるんだお前の思考回路は。
少しはまともに人の話を聞けと怒鳴りつけたくなるが、俺は冷静になろうと敢えて自制を試みた。
こいつの辞書に「傾聴」という言葉は載っていない。その上、人の話を聞き入れるスキルも無ければ、そもそも機能自体が欠落している。
だが、人の短所とて所詮は長所の裏返し。
だとしたら大丈夫だ。問題はない。多分!……一体何が大丈夫で何が問題ないのかは自分でもよく解らなくなりつつあるが。
しかし、それもきっと熱のせいだろう。そうだ。そうに違いない。
およそ0.5秒で以上の思考を終えた俺は、掠れた声でスザクに尋ねた。
「医務室って、どこのだ」
「……軍のだけど?」
すぐそこだし、と、スザクが悪びれもせずクラブハウスの真向かいの方角を顎で指し示す。
――やっぱりか。冗談じゃない!
「軍の助けは借りない!」
ブリタニアに頼るなんて、絶対に御免だ!
そう思うと同時に、俺はベッドから勢いよく飛び起きた。
途端、強い眩暈に襲われ視界がぐるりと反転する。
「……っ! ルルーシュ!」
額に手をやったまま大きく傾いた上体を、スザクが焦ったように支えてきた。
「寝てなきゃ駄目だろ!」
強く叱責されてから思う。
――スザクの前ではあまり言わないようにしていたのに、つい本音が出てしまった。
スザクは「全くもう……」とぶつくさ呟きながら、俺の体を横たえてくる。
「もっとしっかりしろよ。男だろ? 大体、ルルーシュはいつも僕に頼りすぎなんだよ」
「なっ……! 俺がいつお前に頼ったというんだ!」
「頼ってるだろ」
「別に頼ってなどいない! お前が勝手に……!」
「あーそう。そういう言い方するんだ?」
スザクの眉が不機嫌そうにぎゅっと寄せられた。
「お前の言い方の方がよっぽど失礼だろ!」
言い返した俺をじっとりした視線でねめつけながら、スザクがつい、と自分の顎を持ち上げた。
「じゃあ言わせてもらうけど。……いいのか? ナナリーに君が倒れたって言っても」
「お前……っ! 脅迫する気か!」
ぎょっとした俺は目を剥いた。
こいつ、しれっとした顔で何を言い出す!
「別に? だって本当のことだろ?」
開き直ったスザクほど手に負えないものはない。
――この俺に向かって、ここまで偉そうな口をきくのはこいつくらいだ。
半ば切れそうになりながら一言文句を言ってやろうと体を起こしかけると、スザクは「ああ、また!」と怒りながら寝かせようとしてくる。
「別に、俺は平気だ」
「四十度もある病人がなに言ってるんだよ。いいから大人しく寝てろってば。……今、咲世子さんに訊いて保冷材持ってきてやるから」
「……っ!」
勝手にしろと言いたい気分だ。
困り果てたように言うスザクに舌打ちしてから、俺はぷいっと顔を背けた。
なんだかんだ言いつつ、俺を甘やかしているのはお前の方じゃないか。
掛け布の端を持ったスザクが、俺の襟元まですっぽりと覆い隠すように布団を引き上げてくる。どんな顔をしているのか気になるが、まだ振り返ってやる気にはなれない。
暫くのあいだ枕に顔を埋めたまま黙っていると、スザクは俺の顔を確認しようと布団に覆われた肩口をぽんぽんと叩いてくる。
「ちょっとルルーシュ、大丈夫?」
「触るなよ」
「なんだよ……具合悪くなったのかと思って心配したのに」
「余計なお世話だ」
俺に言い返されてうんざりしたのか、もう何度目になるか解らないスザクのため息が布団越しに聞こえてきた。
喧嘩腰になってしまうのは俺のせいじゃない。大体なんだってお前はそう高圧的なんだ、俺に対してだけ!
「君は本当に危なっかしくて見ていられないよ。放っておけなくて困る」
「……そういう台詞は女にでも言ってやるんだな」
ぼそっと言い返した俺に、スザクは「ほら、いいからこっち向けよルルーシュ」と言いながら肩を揺すってくる。
脳が揺れて視界がブレる。
だからお前は……触るなといってるだろう!
「揺らすな馬鹿が!」
本気で余裕を失いかけていた俺は、つい声を荒げた。
放っておけないとか言うんじゃない。頼りすぎだの危なっかしいだの、こいつは本当に失礼な奴だ。
「わけのわからないことを言ってないで、放っておけばいいだろう。別にそれでも構わないんだぞ、俺は」
腹立ち紛れにちらっと布団から顔を出してそっけなく吐き捨ててやれば、ピクリと眉を動かしたスザクはわざとらしく肩を竦めている。
「残念。言葉の綾だろ、それは。女性相手の時は、もっと優しい言い方をするよ。当然だろ?」
馬鹿が付くほどのお人よしのくせに、よく言う。
まあ、場合によっては女相手であっても容赦しない部分のある奴だと俺は知っているんだが。――カレンとかカレンとか、あとはカレンとか。
「心配するなよ。わざわざ言い方を選んだりしなくても、お前はいつだって女に優しいと思われていることだろうさ」
フンと鼻を鳴らしてから嫌味を織り交ぜて言ってやれば、スザクは言葉の意味がいまいち良くわかっていないのか、ぽかんとしながら「それ、どういうこと?」と不思議そうに尋ねてくる。
通じていないとは残念だ。皮肉だよ、この鈍感が。
人の悪意に敏感な俺からすれば考えられない鈍さだが、それもまあ、こいつらしいといえばこいつらしいのか。勘だけは鋭い男だと思っていたのに。
「だからって、こういう甘え方されるのは不本意なんだけど?」
「あまっ……!? 馬鹿を言え! 頼ってなどいないとさっきから言ってるだろ! しつこい奴だな」
「そういう君は可愛くないよ」
「男が可愛くてどうする。気色悪いことを言うな」
「君は昔から素直じゃなさすぎる。僕は、もうちょっと素直な子が好きだよ」
「やめろ馬鹿。俺を女扱いする気か」
「別に、そういうつもりじゃないけど……」
際限なく言い合いを続けていると、なんだかおかしな空気になってきた。しゅん、と音を立てるようにすぼまったスザクの語尾が妙に不穏だ。
「………………」
「………………」
お互い、何故かそれ以上会話を続けることが出来ぬまま、部屋に奇妙な沈黙が落ちた。
「……とりあえず、何か冷やせるもの持ってくるから。大人しく寝てろよ、ルルーシュ」
腰に手を当てたスザクがぴしっ、と人差し指で俺を指差してからくるりと踵を返した。
だから……お前は、と口を開きかけてから俺はきゅっと口を引き締める。
俺はほっと一息ついてから枕に頭を預け、そのまま長い息を吐き出す。……もういい。なんだか全て馬鹿らしくなってきた。
ぱたんと閉まるドアの音を聞いたきり、意識が遠ざかる。
ぼやけた天井に向けられていた視線を無理やり引き離し、俺は急速にまどろみの中へと落ちていった。
オセロ 第29話(スザルル)
29
皇暦2019年、6月。
学生服姿の少年二人が神聖ブリタニア帝国を制圧した。
僭帝ルルーシュ。――全世界に中継された映像によって、傲然と玉座に就いた少年に与えられたそれが、新皇帝となったルルーシュ・ヴィ・ブリタニアへと最初に与えられた世界の評価だった。
たった一日で帝位簒奪劇を成し遂げた二人は今、皇宮ペンドラゴン内、玉座の間から続く天井の高い渡り廊下を歩いている。
強化ガラスで全面に渡って防弾加工が施されたその傍らに広がるのは、燦々と降り注ぐ日の光に照らされた緑の庭園。風雅というより抜けてるなと思いながら、嘗てここを追われたルルーシュは皮肉な想いに囚われるまま口端を吊り上げた。
一見目に優しいこの光景も、本当はいつ何時フレイヤによって消滅させられるか解らない緊張に満ちている。
無論、その事実を知る者は、まだこの二人以外には誰も居ないのだが……。
「潜伏先の情報は?」
一歩後ろを歩くスザクへと振り返ったルルーシュが、つかつかと足早に歩を進めながら言葉少なに問いかけた。
纏う衣装の色は純白。黒ばかりを好んで着ていたルルーシュが『死に装束に相応しい』と誂えさせた皇帝服を見つめていたスザクは、動きにつられて揺れるマントの端からゆっくりと視線を上げてきた。
「本国の文書に記載されている施設については全部調査済みだ。捜索隊からの連絡はまだ……」
返されたのは固く抑揚に欠けた声だった。
騎士服に身を包んだスザクは僅かに眉を寄せている。ルルーシュもまた、予想通りの回答に整った柳眉をひっそりと動かした。
「極秘裏に建設していた施設……恐らく地下だな」
「航空からの捜索も行わせているけど、現段階で上がってきた報告を見る限りでは」
「もしくは海中……。この件に関しては完全に後手だ。捜索範囲を広げたところで無駄に終わる」
「君の読み通りなら、トロモの離反も時間の問題だ。どうする?」
「現状で可能な限りの手は打ってある。離反するならさっさとしてくれた方がこちらとしても都合がいい。脱走してくる機関員を使う。情報提供者への褒賞と保護。情報もリーク済みだ」
互いの靴音が木霊する中、ルルーシュは皇帝服の裾を翻しつつ淀みない足取りで歩いた。
向かう先は、プライベート用に設えられた一室だ。
嘗ての友人同士とはいえ、皇帝と騎士になった二人の間にそれらしき甘さを伺わせる気配は一切無い。
帝国各地で頻発する反乱の鎮圧に奔走していたスザクが、ここペンドラゴンへと帰還したのはつい先程のこと。帝位に就く以前に計画の大略については予め話してあるものの、定期連絡を除けば、ここ数日は話す暇も無いどころか碌に顔を合わせてさえいなかった。
硬質な会話の内容は、即位直後に追討令を発したシュナイゼルたちの所在に関することであり、これから先に控えているのも戦略の内容を密に詰めていく為の打ち合わせだけだ。
辿り着いた部屋に入るなりソファに腰掛けたルルーシュは、向かいの椅子に座ったスザクを前にいきなり本題へと切り出した。
「潜伏先でこちらの動向を伺っている最中だとすれば、動く時期はある程度特定できる。最も警戒しなければならないタイミングが来るとしたらこれからだよ。超合衆国連合への加盟決議前後……いや、前か。内乱の山を越え、国としての大枠が定まった後であれば、対抗策を練られてしまうことくらいは読んでくるだろう」
言いながら足を組んだルルーシュは、テーブルの上に置かれた資料を手に取った。
「旧ラウンズたちの潜伏先については割れたよ。俺は先にそちらを叩いておくべきだと思うが」
「来るさ、向こうから。その前に国内の平定だけでも終えておきたいところだが、今の状態が続くようではまず無理だろうな」
遠征が重なった疲れもあるのだろうが、スザクの声は相変わらず平坦で感情の色に乏しいままだ。
不謹慎極まりないと解っていながら、手元の資料に目を通していたルルーシュはクスリと笑った。
騎士と皇帝。――互いに装っているこの仮面ですら、どこか滑稽に思えてくるのは何故なのか。
「即位早々、ブリタニア臣民からの俺の評判は地を這っている。これも予定通り……だが、まだほんの序章だ」
笑った理由を摩り替えることにはどうやら成功したようで、スザクは生真面目そうな顔をほんの少しだけ和らげた。
「貴族制度の解体と、ナンバーズ制度の廃止……」
「ああ。当然それだけで終わらせるつもりはない。全臣民を奴隷化する計画は既に開始されている。他国の奴らもそろそろ気付き始めるさ。法改正という名の下に仕掛けたられた巨大な落とし穴に……。ゆえに起こる反乱。その為の所信演説だ」
――そして、いずれは全世界が奴隷と化す。
怜悧な眼差しをふっと緩めたルルーシュを見て、スザクは和らげた表情を再び凍てつかせる。
(本当に、不謹慎極まりないな)
ふっと心を閉ざしたスザクを前に、ルルーシュは自嘲も已む無しと考えた。
自ら被った悪の仮面でさえ、引き起こした行動の結果によって、こうして本物の顔と同化していくのだから。
けれど、今のルルーシュは「何が可笑しいのか」と問われれば「何も可笑しくなどない」と本心から答えるだろう。
それが、一年前のルルーシュとの大きな違いだった。
(命を賭けたゲームだからこそ、本気でやる価値がある)
心の中で唱えたのは、敢えての確認。
悪逆皇帝の剣として日々多くの命を奪い続けているスザクにとっては、こういったズレた感覚など皆無なのだろうが。もしかすると何かのゲームか、でなければ、ごっこ遊びの延長なのではないかという錯覚すら起こしそうになる。
……あるいは、冷静に狂気を装うとは、そういうことなのだろうか。
だとしても。
(踊り続けてやるさ。終幕の瞬間まで)
地獄の釜の蓋を、自ら開けた者として。
これは悲劇か、はたまた喜劇なのか。どちらも嘘ではないのだと、多分お互いが解っているのだけれど――。
「ランスロットの調整は?」
「予定通りだ。近日中には。MVSは以前と変わらず実戦投入しているけど、エナジーウイングと新型ヴァリスの微調整がまだ残っている」
「その為にも、お前には一度戻ってもらう必要があった。元貴族たちの討伐には、今ジェレミアを向かわせている」
「俺は強襲に備える」
「そういうことだ。お前には暫くこっちに居てもらう」
「……シュナイゼルが国内の反乱を統合してくる恐れは?」
「その線は無い。旗頭になれるほどの目ぼしい勢力も居ないことだしな」
「解った」
静寂が訪れるのを無意識に拒む二人は切れ間無く会話を続けていた。合間に、ルルーシュがテーブルへと資料を置く。
パサリと音を立てた紙束に目を向けたスザクが無言でルルーシュの言葉を待つ間、暫し固い空気が両者の間に流れた。
ルルーシュはまだ残るぎこちなさを隠したまま息を詰め、スザクを一瞥してから、
「ラウンズたちの迎撃時には映像を全世界に放映する。超合衆国への参加表明もその時だ。――勝てるか?」
「イエス・ユア・マジェスティ」
腕を折り、恭しく右手を胸に当てたスザクに、ルルーシュが小さく頷く。
畏まるスザクの姿を目にするのは幾度目のことだろう。透き通った翠玉は思い詰めたように眇められ、敬意と全幅の信頼、そして厳格なまでの覚悟だけを表しているように見える。
詰めた息を静かに吐き出しながら気だるげに背凭れへと身を預けたルルーシュは、「では次だ」と口にしながら緩やかに足を組み換えた。
「超合衆国との交渉の舞台だが……俺は、アッシュフォード学園を指定しようと思っている」
唐突なルルーシュの宣言に戸惑ったのだろう。体の横へと手を下ろしたスザクの動きがはたと止まった。続けて漏らされたのは「え?」という純粋な驚きの声だ。
ルルーシュは悪戯っぽく、鼻先を見る角度でスザクへと斜めに視線を向ける。
「理由は二つある。交渉と銘打ってはいるが、目的は乗っ取り。緩衝地帯であれば向こうも是と言わざるを得ない」
椅子の上で身じろぎしたスザクが向き直り、訝しげに眉を寄せてきた。
「しかし、何故わざわざアッシュフォード学園を? ギアスを使うにしても、あそこはまだ機情の監視システムが生きている。黒の騎士団も駐留している以上、下手な真似は出来ない」
その答えにまんじりともせずルルーシュは頷く。予め予想していた返答ではあったのだろう。ソファに深く腰掛けたまま腕を組む動作は緩慢なものだったが、ふと思い出したように目頭へと触れてから言った。
「ギアスの情報がどこまで漏れているかは正直なところ未知数だ。だからこそ、悪用を避けて止めておくことを奴らは選ぶ……。それに、これは世界を敵に回すための算段。ギアスを使うまでも無い」
コンタクトに覆い隠された両目から手を離し、こともなげにルルーシュは言い切った。
見る者に「至高の紫玉」とさえ評されてきたルルーシュの瞳。――しかし、それはもう嘗ての色合いを残してはいない。
「超合衆国への参加を表明してみたところで、まともに決議が通らないことなど自明の理。例の最高評議会システムについてもそうだが、そもそも合衆国憲章の条文でさえ、設定したのは他ならぬ俺自身なんだからな。その上で正面から直属軍を伴って赴くなど論外だ。丸腰で来たとアピールすることこそが重要なんだよ」
それまでルルーシュの一挙一動をずっと無言で見守っていたスザクは、複雑な表情を隠すように顔を背けた後、少々思案してから呟いた。
「では、奇襲でもかけるつもりか……?」
「正解だ」
答えたルルーシュがにこりと笑った。顔にかかるサイドの髪をかき上げながらスザクの方へと振り返る。
「その為にも、わざわざ駐留させられて動きづらい他国ではなく、単身で来たと見せかける必要がある。その点でアッシュフォード学園はベストだ。立地条件が格段にいい。幸い、周りも海に囲まれていることだしな……」
懐かしげに細められていたルルーシュの瞳に、その時ふと不穏な色が混じった。だが、それでもスザクは口を挟もうとしない。
「直属軍は海中にて索敵を避け、お前はアヴァロンの上から更に離れた上空にて待機。俺の合図と同時に校舎に突っ込む。――シンプルな方法だろう?」
「……つまり、加盟を認めても、認めなくても?」
「そう。そこで両取り(フォーク)だ」
冷えた声で呟くルルーシュへとスザクは不思議そうに尋ね返した。
「両取り? 各国代表を人質に?」
「それは最初から一つ目の理由の方に組み込まれている。確保すべき重要な駒なら、他にもう一人居るじゃないか」
「もう一人……?」
「ニーナだよ」
言い終えたルルーシュが不敵に笑った。
組んだ手元ごと身を乗り出して前屈みになっていたスザクは、又もはたと動きを止めてから顎を引く。
「そうか……日本はブリタニアと超合衆国の中立地帯。検問も動かせる」
「ああ。ニーナはフレイヤ対策には絶対欠くことの出来ない最重要人物。彼女を確保するためというのが、二つ目の理由だ」
ルルーシュは「ミレイ会長にも謝らなければならないな」と口にしてから、おもむろに席を立った。
スザクはどこへいくのかと首を巡らせて見ていたが、ルルーシュは冷蔵庫の中から取り出したミネラルウォーターをグラスになみなみと注いでから戻ってくる。
スザクの前にもグラスが置かれ、目を丸くしたスザクは弾かれたようにルルーシュを見上げた。
「別にいいだろ、これくらい」
ルルーシュがグラスとこちらとを見比べているスザクに向かって困り顔で眉を下げれば、スザクは僅かな沈黙を挟んでからグラスを手に取り「ありがとう」と小さな礼を返した。元の位置に腰を下ろしたルルーシュは、聞きつけた礼に対しては何も答えぬまま冷たい水で喉を潤している。
話し続けているうちに、随分と喉が渇いていたようだ。スザクもそれは同じだったようで、グラスの中身を一気に飲み干し空にしていた。
ルルーシュはその間黙ってスザクの様子を眺めていたが、そのうちゆっくりと目を逸らしてから組んだ膝の上にグラスを立て、手にしたそれを戯れのように揺らしたり傾けたりする遊びに興じ始める。
そうして、暫くしてから口を開いた。
「貴族の位を剥奪しただけに留まらず、学園の校舎まで派手にぶっ壊すことになるとはな。恩を仇で返すとは正にこのことだ」
フレイヤでも被害を被ってはいたが、消滅したのはクラブハウスだけだ。
それを思い出したらしいスザクは一瞬表情を曇らせはしたものの、冗談めかしたルルーシュの口調を内心本気だと受け取ったのだろう。「後悔を?」と尋ねてきたが、ルルーシュは薄く笑ったまま「まさか」と答えるだけだった。
「俺たちは事実上中退したも同然だが、母校を守るのも生徒会役員の務めだろ? 何のために学生服姿なんかでパフォーマンスしたと思ってるんだ」
ブリタニア入り前日にルルーシュが言い出したことを思い出したのか、揶揄する口調にスザクも「そういうこと?」と呟きながらようやく相好を崩した。
……もっとも、それはほとんど苦笑いにも等しい表情ではあったが。
「『久しぶりに着たくないか?』なんて言い出すから困惑したよ。一体どうやって調達したんだ?」
「ちゃんと国内に入ってから買ったに決まってる。サイズもピッタリだっただろ?」
得意げに答えるルルーシュは「当然だ」とでも言わんばかりに胸を反らしている。いつも通りの不遜さを崩さないルルーシュの調子に、スザクも浮かべた笑みを深くした。
「そうだね……。君は突飛に見えても、実は計画的だから」
スザクは「逆な場合もあるけど」と付け足してから、
「でも、本当は何か他にも理由があるんだろう?」
と、ルルーシュがしれっとした顔でグラスを空けているところへ的確に核心を突いてくる。
「相変わらず鋭いな、お前は」
含んだ水をこくりと飲み下してから目を瞠ったルルーシュが、口元に薄く刷いていた笑みを消してスザクを見た。
スザクは「長い付き合いだからね」と答えながらも、翳りのある表情で瞼を伏せている。
ルルーシュは両手でグラスを包み込んだまま、遠い目をして呟いた。
「学園は残させるさ。地上の楽園だからな、あの場所は。……だから取り戻すんだ。俺たち二人の手で」
「――――」
慈しむようなルルーシュの声に顔を上げて何かを言いかけたスザクだったが、言葉にならなかったのかすぐに俯く。
「……学園の、生徒会の皆は?」
「生きている」
「それは、誰から?」
「リヴァルだよ。会長にニーナ……それから、カレンも」
「カレン……」
スザクは昏い表情のまま、重々しくその名を口にした。語尾を引き継ぐようにルルーシュが言葉を続ける。
「お前が倒すのはあくまでも紅蓮だ。あれさえ壊せればいい。ギアスがかかっている以上お前が易々と死ぬことはまず無いだろうが、ダモクレス攻略の際にはくれぐれも上手く負けてくれ。でないと――」
「ああ。解っている」
途端、顔を上げたスザクの瞳に力が宿る。
真に迫った空気の中、ルルーシュも重々しく首肯を返した。
「ゼロ・レクイエムのために」
「イエス・ユア・マジェスティ」
一言呟いたルルーシュに向けて、スザクはもう一度掌をさっと胸の上に翳した。
ルルーシュはそんなスザクを満足げに見遣ってから、手遊びのようにずっと触れていたグラスの表面を眺めている。嵩の減った水面が、透き通ったクリスタルの中でゆらゆらと揺れていた。
何気なく置かれている物も含め、室内の調度は全てが一級品だ。今二人が使っているグラス一つとっても、ただ触れているだけで掌にひんやりとした感触を伝えてくる極上の名品。
シャープなカッティングが施された底面は重厚。対する飲み口はというと、爪で弾けば涼やかな音を立てそうなほど繊細な薄さを保っている。
……しかし、先程からルルーシュが魅入っているのは、美しくカットされた模様などではない。
角度を変えるたび、部屋の照明を反射してキラキラと輝く硝子。
どんなに高価な宝石の輝きよりも、硝子の放つ透明な煌きの方が余程美しいとルルーシュには思えた。
スザクはグラスを傾けるルルーシュの姿を無言で見守っている。……だが、相変わらず何を考えているのかはいまいち判然としない。
決してまがい物ではない白い光をじっと見つめながら、ルルーシュは再び話し出す。
「世界統一後、日本は皇帝直轄領とし、ゼロ・レクイエム後に独立させる。ブリタニアの暫定代表はお前だ。国交正常化交渉締結後に新代表を選出。人事に関してはお前に一任する」
ルルーシュは自分自身の死後に関する計画を、明日の天気について話す時のように口にした。
救世の英雄・ゼロとして、スザクはその後も世界平和の為に、命ある限り政治の第一線にて尽力し続ける。
……しかし、その世界の中に、ルルーシュが求めた明日の中に、ルルーシュ自身の姿は無い。
常人の精神では決して平静に振舞ってなどいられないであろう重いプレッシャーの中、それでも平然とグラスを玩びながら話すルルーシュをスザクは不安そうに見つめていた。
「だが……本当に可能なことなのか? それは」
スザクが言い出すのも無理はない。それは事後を託される者として当然の疑問だった。
問題は、世界平定後の人事だ。身分制度廃止後の皇族たちに政治的実権はなく、新たに選出するにしても問題が山積みなのである。
それに、スザクはそもそも肉体的な労働にしか従事してきたことがない。そのスザクに対して、いきなり一国のみならず世界情勢そのものを左右する重責を一人で担えというのはあまりにも酷な話だ。
ルルーシュは一呼吸おいてから、ちらりとスザクを一瞥した。
「補佐にシュナイゼルを付ける」
「……!」
両膝の間で手を組んで座っていたスザクが、ハッとしたように全身を強張らせる。
――それは、これから討つべき敵の名だ。
スザクは一瞬我が耳を疑った――が、しかし。ルルーシュが述べてきたのは疑問に対する回答の全てを集約させた一言だ。
たった一言だけでスザクは全てを理解し、そして納得した。
「生かすのか。ギアスを使って」
スザクが硬質な声で呟く。
ルルーシュはそれにこくりと頷きを返しながら、底を持ったグラスを掌の中でくるりと器用に回してみせた。
こぷんと音を立てながら、グラスの中で水が踊る。
「策はある。――それに」
ルルーシュは言い置いてから、端正なその顔に冷然とした気配を漂わせた。
辺りの温度が二、三度は下がったような体感。だが、ルルーシュの瞳に浮かぶものは明らかな怒りの炎だった。触れれば即、凍傷にもなりかねないほどの凄絶な冷気を周囲に撒き散らしておきながら、ルルーシュ自身は全身の血液が煮え滾るような凄まじい怒気を内在させ、押し殺している。
「あの男にも罪がある」
諸悪の根源が、この俺自身であることとは別にしてもだ。――と、付け加えたルルーシュを見たところで、スザクの真剣な表情は変わらない。
ただ一言、静かな声で「それで?」とだけ尋ねられ、ルルーシュはふと我に返ったように「ん」と瞬いた。
「理由は本当にそれだけか?」
「理由……?」
「うん」
スザクは何らかの確信をもって強く頷き、まっすぐな瞳で凝視してくる。
「最初から無駄なことをしようとするような君じゃない。追われている身にも関わらず、わざわざ買ってまで用意するくらいだ。本当はそれなりの理由がもっと他にあるんじゃないのか?」
「――――」
よく観察された上での的確な推論に、ルルーシュが一瞬口ごもる。見解に対する答えを求めているのか、スザクは何かを訴えるようにルルーシュを射抜いた。
「それに、いくら大胆に振舞っていても、君は基本的に慎重派だ」
古くからの知己であるからこその指摘なのだろう。確かにその意見は正しいと判じながらも、ルルーシュはとりあえず笑っておいた。
「やけにはっきり断言してくれるじゃないか」
「でも、そうだろう?」
「確かに否定はしない」
ルルーシュが曖昧に答えると、スザクはルルーシュを見つめたまま「それに」と続けた。
「君は、一回の行動で出来るだけ多くの目標をクリアしようとする。一つや二つで済む訳ないよ」
「…………」
さすがによく解っているとでもいうべきか。ルルーシュは思わず閉口した。
ここまで見切られてしまうと笑うしかない。……それに、こうして追求されることで何かを思い出しかけたような気もする。
過去へと繋がる、これは既視感だ。
スザクがどこまで察した上で聞き出そうとしているのか危ぶむ気持ちはある。――が、しかし。
スザクは理解している。そう判じたルルーシュは、感じたデシャヴュをわざと無視して口を開いた。
「知って欲しかっただけだよ。たった二人の学生にも、世界を変えられるだけの可能性があるのだと。本来、そういうことだろう? 生きるとは」
ルルーシュが自分の手元へと視線を落としながら、今度は腿の上に立てたグラスを左右に傾けて遊んでいる。
穏やかなルルーシュの問いかけにスザクも柔らかく頷き、次いで、囁くような声音で淡々と述べた。
「解っているだろう、ルルーシュ。今の俺は君と同じだと」
「……だからこそ、説明は不要かと思ったんだが?」
「気付いているくせに、まだそんなことを? 理由に理由が必要なのか?」
ルルーシュは目を閉じて軽く笑った。
「……まあ、そうだな」
スザクの申し出を聞き入れたルルーシュは、細く吐息してからようやく語り出す。
「あれは単なる啓発だ。世界に自立を促すための……。支配する側は当然悪だが、人々は知る必要がある。体制に阿り支配に甘んじることも、また悪なのだと。支配者と被支配民という二分化の構図。身分格差が生んだ世界の歪み、既存の間違ったシステム。あれは、そういったもの全てに対する反逆でもある」
スザクは先を促すように、更に台詞を繋いだ。
「支配を許すとはどういうことか、思い知る必要がある……?」
ルルーシュは意図を集約してきたスザクの発言に「そうだ」と鷹揚に頷いてから、
「お前たちはそれでいいのか? という問題提起だよ。つまりはな」
と、スザクに向かって簡潔に答えを述べてやる。
おそらくルルーシュの物言いについて何か思い当たる節が自分の中にもあったのだろう。聞きつけたスザクは曲げた唇の端からふっと息を漏らした。
「……たった二人の学生に支配される世界か」
背を屈めたまま俯いたスザクが低い声で呟く。吐き出されたそれは、紛れも無い自嘲だった。
常のスザクらしくもなく、皮肉っぽい独白。自分のことを『僕』と呼んでいた頃には見られなかった姿だと思いながら、ルルーシュは笑んでいたスザクの口角が下げられていくさまをじっと見つめていた。
「それはそうだろう。だからいいんじゃないか。暴君だと一目で解るだろ?」
ルルーシュはいかにも挑発的な口調で語りかける。
しかし、酷薄そうに歪められた唇とは裏腹に、瞳の奥に見え隠れするものは紛れも無い愁い。対するスザクはというと、これもまた沈鬱そうな真顔だった。
スザクがゆっくりと顔を上げてくる。偽悪に徹するルルーシュの姿を目の当たりにして、スザクもまた――。
けれど、もう一度とようやく微笑んだその顔ですら、果てしない悲しみと苦渋の色に満ちていた。
聞く者が聞けば正気とも思えないような話だが、生憎この二人は本気なのだ。
スザクは悪辣な笑みを浮かべているルルーシュへと、落ち着いた声音で問いかける。
「隷属を望み、自己不在のまま追従したがる者も悪……。そういうことだろう? 君が言いたいのは」
「…………」
真顔に戻ったルルーシュは、その問いには答えない。話すスザクを心持ち険しい目つきで眺めていたが、突然ついと視線を逸らした。
スザクは構わず話し続ける。
「啓発というより挑発と言った方がわかりやすいとは思うけど……それも全て、反逆という括りに収めてしまうのか?」
「……そうだと言ったら?」
「やっぱり、君はガサツだ」
スザクは軽く肩を揺らした。
困った人だとでも言いたげな優しい口調。声音に滲む懐古の念。
暫くの間、横目で咎めるような眼差しを送っていたルルーシュだが、やがて諦め混じりに嘆息した。
それ以上は何も言うなと牽制されていることに気付いていながら、スザクは尚も引こうとせずに言い募る。
「確かに楽だったよ、人に従っている方が。自分でありたくなかったのは俺も同じだ。今の世界と……」
「……………」
ルルーシュは気まずい思いをどうにか抑えて黙り込んだ。もう一度手元のグラスに目をやってから、こくりと一口水を飲み込む。
別に、どうしてもという訳ではないが――だから聞かせたくなかったのだ。
「今のが『理由を言わせたかった理由』か? スザク」
ルルーシュが組んだ足のつま先を揺らしながら皮肉っぽく尋ねると、解っているくせにとでも言いたげなきつい視線が返された。
スザクは左右にかぶりを振ってから、
「ルルーシュ、俺たちは共犯者だ。――だったら」
「秘密主義はもう終わり……そういうことだろ?」
促されて答えたルルーシュはふんと笑い、、勘弁してくれとばかりに肩を竦める。
スザクがたった今口にした台詞は、嘗て式根島でルルーシュがゼロとしてスザクへと突き付けた言葉だ。スザクは開き直りでも居直りでもなく淡々としているが、口に出せば例の過去について嫌でも想起させることになるだろうとは思っていた。
とりたてて伏せようと思っていた訳ではなくとも、詳細については敢えて言わずにおこうと思っていたのもそのためだ。
ルルーシュは仕方なく、フォローするかのようにぼそりと呟く。
「お前は、お前自身のルールに従っていただけだろう」
「そうだ、ルルーシュ。だから変な遠慮はいらないよ」
渋面を作ったルルーシュに、スザクはここぞとばかりに告げてくる。
「そんなつもりじゃない」
ルルーシュは居心地の悪さを誤魔化すように嘯くものの、スザクはどうやらまだ言い足りないらしい。
「俺が気付いていないと思っていたのか?」
「別に……そんなことは思っていない」
歯切れ悪く呟いたルルーシュを見て、スザクは困った顔をしながらすとんと背凭れに寄りかかった。
「君は変わらないな」
「ああ。俺は俺だからな」
強気な答えに「らしい」と思ったのか、スザクの口元がほんの少しだけ緩んだ。
ルルーシュはまたも仕方なく話し出す。
「……もう随分と前のことだ。俺が『想いの力』などという、抽象的かつ曖昧なものを信じてみたくなったのは――」
ルルーシュがようやく空になったグラスをテーブルへと下ろした。置かれたグラスの底が、ことりと音を立てる。
表面に水滴の残るグラスの縁を、ルルーシュはそっと指先で辿っていた。グラスを撫でるルルーシュの指は男にしては華奢と表現してもいいほどの細長さで、時折見せる動作も酷くいとけない。
けれども、それでいてルルーシュは人一倍貴かった。か細いその背中の上に、自分一人きりでは決して抱えきれないほど多くの命を背負いながら、今も尚。
銃よりも鍵盤の方が良く似合いそうな白い指先は、まるで触れれば溶ける雪のような儚さだ。はらりと綻ぶ真白き花弁のようなルルーシュの姿を、スザクは無表情で見つめていた。
ルルーシュが纏っている皇帝服の色と同じ、白のイメージ。その印象こそが、今在るルルーシュ自身の本質――心の内側に存在する核という、彼自身の高い精神性そのものを表していた。
やがて、沈黙していたスザクはルルーシュから目を逸らして、
「とは言っても、君のことだ。そう昔ってほどでもないんだろう?」
と、穏やかな声で尋ねた。
ルルーシュはクスリと苦笑して、指先に付いた水滴を邪魔くさそうに弾いている。行儀悪く辺りに水しぶきを散らすそのさまを見て、スザクは珍しそうに眉を上げていた。
「そう、あれは……合衆国中華を進言した折のこと。天帝八十八陵での戦闘終了後だ。お前もあの場にいただろう?」
「ああ」
向けられたルルーシュの視線に合わせてスザクが首肯する。ルルーシュはまだ湿り気の残る手を組み合わせ、自分の膝を支えに肘をついた。
やや上体を屈め、余所へと向けられた眼差し。そして、組んだ手で覆い隠された口元。
顔や胸の前を遮ろうとするのは心の内側を知られまいと構えている証拠だ。ルルーシュは、自分でもそのことに気付いていながら手を退かそうとはしなかった。
その代わり、
「星刻と和解した時だ。人の想いを信じてみたい、見てみたいと、俺がそう思ったのは……」
滅多に本心を吐露することのないルルーシュの言葉に、スザクは眩しげに目を細めた。
「人を信じないのは、子供の頃からの君の悪い癖だよ」
「…………」
やんわりと指摘されたルルーシュは沈黙し、スザクがそれを破った。
「君は泣きたかったのか? ルルーシュ」
「―――!」
瞬間、ドキリと胸が高鳴った。
ルルーシュはハッとしたものの、硬直していると気付かれないよう体の動きを止めたまま何も答えず、表情も変えない。
ただ、一度だけスザクを見遣ってから閉じた瞳をゆっくりと見開き、表した紫玉を下へと落としただけだ。
そうして、考えた。
もう二度と口にはしないと決めた想いがある。だから、心の中での線引きはどうしても必要だった。……けれども、それが思った以上に難しいのだ。
今交わしている会話とて、本来ならば特に話す必要の無いこと。開示出来る範囲や限度などとっくに超えているようにも思える。
(もう充分なんだ。俺にとっては)
識り合うことが出来た。変わり合うことも……。本当に充分すぎるくらいだと心から思えるほどに。
ただ、『共犯者』となった者同士、決して振り返るべきではない過去がある。
それを「もう要らない」と切り捨てる訳ではなくとも、スザクの気持ちを考えれば、心の奥底に触れるような会話を交わすのはなるべくならば避けておきたかった。
言うまいと決めた想いがあるのなら、尚のこと――。
(否定するのは簡単だ。だが――)
吐き出した溜息ですら聞き咎められはしないかと戸惑いながら、ルルーシュは結局、悩んだ末にぽつりと呟いた。
「……覚えていたのか」
「まあね」
「自分で忘れっぽくないと言うだけのことはあるな」
そう言ってやれば、スザクは黙ったまま目元を和らげている。
軍人としての影響というより、幼い頃から武道全般を極めてきた名残なのだろう。足を組んでいる姿など見たことはないが、一人掛けの椅子に浅く腰掛ける姿勢でさえもきちんと背筋が伸びていて、見るからに律儀そうな印象を周囲に与えている。
(迂闊なことを言うものではないな)
そんな所もスザクらしいとぼんやり考えながら、ルルーシュは内心自省した。スザクの問いかけは、ルルーシュが潜伏中に何気なく口にした一言だ。
――まさか、こんなことを訊かれるなんて思ってもみなかった。
「お前やナナリー以外を、本当の意味で信じようとしたことなど無かったからな。俺は」
スザクの姿を視界の端で捉えながらルルーシュが告白する。
真の意味で自立から程遠いところにいるのだとルルーシュが悟ったのは、スザクとの別離を受け入れてからのことだ。
身内と他人。……本当は、ギアスのことを詳しく知らされる以前から、ルルーシュの世界はいつだってそんな風に切り分けられていた。
白か黒か。そこにグレーという選択肢は無い。
自身ですら灰色となって溶け合うことをひたすらに拒み、ルルーシュの心は常に二極化され続けるばかり。そして、最後にはとうとう黒く染まり切ることだけを選んでしまった。
懐へと招き入れることで、一旦身内だと判じた者以外を、決して心の深部まで迎え入れることも無く――。
(スザクは身内だった。ずっと)
ルルーシュにとって、唯一の。その想いは今でも変わらない。寧ろ新たな関係へと創りかえることによって、より強くなったとさえ言えるのかもしれない。
培われた経験の蓄積が人を象っていくというのなら、その生き方以外選べなかったなどと殊更悲劇ぶってみる必要は無いし、ましてや、否応無く人生に流され続けてきただけなのだと思うことにも意味などないのだろう。
ルルーシュはもう、そんな風には思わない。……いや、思えなかった。
(選んだのは俺だ)
悔いはある。慙愧に耐えない後悔の念が。
しかし、安易に自己卑下へと走る醜悪を、ルルーシュの潔癖さは頑なに拒否する。
時折立ち尽くすことがあったとしても――嘆き悲しむ心の内側を無視してでも、決して歩みを止めることなく進み続けてきたルルーシュ自身の過程こそが、何よりも明確に意思の在処を示していた。
ただ、ルルーシュにとっては新たな形でやり直したいと願うことも、実際にやり直せると思えることも、今はもうこれだけなのだ。
だからこそ、ルルーシュは振り返らないし自問もしない。
『大切なのは手段』
スザクに言われたあの時に、立ち止まれる自分であったなら、などと――。
自ら選ばざるを得なかったのがこの生き方でしかなかった事情を考慮するにせよ、それとて只の言い訳だとルルーシュは思う。
幼い頃から、知らず頼り続けることで背負わせすぎてしまっていた。……例え、実際に助けて欲しいと口にしたのが、たった一度きりのことであっても――。
長いこと物思いに耽っていたルルーシュが、やがて独白する。
「先に自立されていたことを受け入れられず、ずっと拒んでいたのは俺の方……。ただ、それだけのことだ」
スザクが生真面目そうな顔をこちらに向けてくる。視線を感じてはいたが、ルルーシュは伏せた顔を上げることはしなかった。
「ルルーシュ」
「…………」
スザクの呼びかけにも、ルルーシュはやはり俯いたまま答えない。――何を言われるのか、なんとなく察していたからだ。
「君は……。だから、この計画を?」
「馬鹿を言え」
途端、ぱっと顔を上げたルルーシュは、ぎゅっと眉根を寄せてスザクを睨んだ。
「勘違いするな」
「………………」
テーブルを挟んで斜めに向き合う二人は互いに譲ろうとしない。
複雑な感情を胸の内で渦巻かせているのはルルーシュだけではなく、きっとスザクも同じなのだろう。膝の上で握られているスザクの拳に気付いたルルーシュは、不意に顔を歪めてそこから目を背けた。
つい先程、ルルーシュが触れていたグラス。まだ水滴で濡れているその表面を見つめてから、スザクがゆっくりと唇を開く。
「安心しろ、ルルーシュ。君の覚悟を穢すつもりはない」
「……だったら何だ」
ルルーシュが低く尋ねると、スザクは表情をぴくりとも動かさぬまま一度だけ瞬いた。
それから、何を考えているのか全く読み取れぬ顔つきでルルーシュへと向き直り、そして言った。
「俺はただ、気付けていたのかと思っただけだ。君が泣きたかった本当の理由に……」
「――――!」
ルルーシュはこれ以上無いほど大きく目を見開き、絶句した。
僅かに仰け反らせた上体に震えが走り抜け、指先がすうっと冷えていく。
だが、ルルーシュは二、三度ほど目をしばたたかせてからすぐに正気を取り戻した。
「よせ、スザク」
「ルルーシュ、」
「俺たちは『共犯者』だ」
そうだろ、と目配せしながら、ルルーシュはスザクが短く名を呼ぶ声に覆いかぶせるようにして遮った。眉間に刻んだ皺を更に深めながらスザクをねめつけ、往なすようにわざと突き放す。
「ルルーシュ……」
不意に、スザクの顔が悲しげに歪んだ。
「……っ」
正視に堪えなくなったのか、息を飲んだルルーシュはそれきり力無く肩を落として項垂れた。スザクはそんなルルーシュの姿を見て眉を寄せていたが、噤んだ唇を真一文字に引き締めたまま続く言葉を辛抱強く待っている。
一旦俯いたルルーシュは苦悶の表情を素早く無へと切り替え、毅然と顔を上げてからスザクと目を合わせた。
「スザク……俺は満足しているんだ、今の関係に。それに、まだ何も終わってはいない。これからだ」
諫める響きで言い募れば、今度はスザクが握り締めた拳へと力を込めながら目線を下に落としていく。
その途中、ちらりと上げられたスザクの瞳が捉えたものは机上のグラスだった。――但し、それはルルーシュのものではなく、スザクの前に置かれていたもの。
スザクは名残惜しさを断ち切るようにそこから目を引き離し、そのまま黙り込んだ。
……一部始終をしかと見届けていたルルーシュの中で、痛ましい想いが疚しさへと変換されていく。
ルルーシュは、今も尚変わらぬスザクの優しさをひしひしと感じながら思った。
年月を経たところで変わらないものはある。表層的にはどうあれ、個人主義というスザクの根幹は変わっていなかった。
それでも時の針は進み続け、常に変化し続けていく。――世界も、そして、人も。
ならばきっと、スザクにとっては重荷でしかなかった筈だ。
『お前なら協力してくれるだろう』
そうやっていつまでも自分、ルルーシュに乞われ、頼られ、甘えられ、そして心理的に依存され――まるで永遠を追い求めるように変わらぬ関係性をずっと求められ続けるのは……。
ルルーシュはスザクの柔らかそうな癖毛をじっと見つめていた。こうしてただ見ているだけで、いつかこの手で触れた時の感触が蘇ってくる。
こみ上げる何かを堪えるように大きく上下していたスザクの背中。それは今既に落ち着きを取り戻し、静かに沈黙を保ってはいたけれど――。
やがて、スザクは暗く翳らせた顔をようやく上げてきた。凪いだその表情は細められた翡翠と同様どこか空虚さを帯びていたが、スザクは何を思ったのか突然ぽつりと漏らしてくる。
「君が俺の前で泣いたのは、三回だ」
まだそんなことを、と思いながら、ルルーシュはスザクへと無言で非難の眼差しを送っていた。
「三回……?」
それでも尋ね返したルルーシュに、スザクは「子供の頃を除けばだけどね」と補足のように継ぎ足してくる。
再会してからのことを言われているのだと気付いたルルーシュは思わず「二回だろう?」と訊き返しそうになったが、寸でのところで思い止まり、反芻した記憶の中でその回数を数えた。
(あ……)
思い当たるまでに、然程時間はかからなかった。
何故か今までずっと二回きりだとばかり思っていたのは、去年のバースデーにスザクと会った時の記憶が抜けていたからだ。
決して忘れていた訳ではない。覚えているし思い出せる。……すぐにでも。
それなのに、ルルーシュは自分でもいっそ不思議に思えるほど自然に「二回きりだ」と思い込んでいた。
きっと、のち二回の記憶があまりにも鮮明すぎたからだ。
……と、思い返したルルーシュは直後に打ち消した。
(違う)
本当は――。
ルルーシュは呆然としたまま眼前のスザクを見つめた。急速に現実感が遠ざかり、みるみるうちに過去へと立ち返っていく。
意識的に避けてきた既視感。……それはまるで、白昼夢のような。
(そうだ。忘れていたんじゃない。俺は――)
一年前のことでさえ、あまりに遠く。
けれどルルーシュの明晰な頭脳は、こんな時でさえ勝手に結論をはじき出す。
ルルーシュは辿り着いた自らの答えに愕然とし、くらりと世界が回った気さえした。
――忘れたかったのだ。耐え難い痛苦を伴う記憶だからこそ。
だから無意識に追いやっていた。記憶の片隅へと。
……何故なら、ルルーシュにとってはあの夜こそが、スザクとの別離を決定的なものにしてしまった記憶だったのだから。
ルルーシュは貪欲だった。――確かにその筈だった。
どんなに酷い記憶も、どんなに凄惨な過去も、全ては自分自身のもの。
知人、友人、兄、姉、弟、妹、両親、そして名も知らぬ人々。
奪い続けてきた大勢の命。
果ては、今この世界に渦巻いている悪意、憎しみ、怨嗟の声でさえも、全てがルルーシュのもの。
そうなるよう望んだのも、仕組んだのも、今仕向けているのも、他ならぬルルーシュ自身だというのに。
(その俺が、忘れたがっていた? 手放したがっていた? それとも、逃れたがっていたというのか?)
何故?
(そんなことは、ありえない。あってはならない)
――それなのに。
「……ルルーシュ?」
目の前でスザクが何か喋っている。すぐに反応しなければおかしく思われてしまう。
ルルーシュは焦った。……けれど、意識が剥離していて実感が伴わない。
「ぇ――?」
喉から漏れたものは、声というにはあまりにか細く、掠れた音だった。
内側から湧き上がるものと、それを無理やり押し戻そうとする意識。
……その合間で、ルルーシュは目頭を手で覆いながら泣いている自分自身の姿を見たような気がした。
心臓の動悸が早い。耳の裏に走る血管がドクドクと音を打ち鳴らしている。全身がかあっと熱くなり、その直後、血の気が一気に引いていった。
ルルーシュはたった今見えたそのイメージをかき消そうと、スザクを見つめたまま数回瞬きをする。それで少しでも気を確かにすることが出来れば――そう思った。
「なんだ、スザク?」
気付けば、ルルーシュは踏み込むだけで開く自動ドアのように答えていた。
スザクは少しだけ不思議そうにしていたものの、気を取り直したように口元を綻ばせる。
「どうしたんだ? ぼうっとして」
「ん? いや……なんでもない」
ルルーシュが平静を装ってかぶりを振れば、スザクは懐かしげに瞼を伏せてから呟いた。
「色々あったな。俺たちは」
「――――」
過去を懐かしむその声も口調も、まるで昔話を語っているかのようだ。
ルルーシュは答えない。というより、何も答えられなかった。
その様子を傍で見ている限りでは、単に答えるのを拒んでいるようにしか映らないのだろう。スザクは凪いだままの顔に諦めの色を滲ませながら、それでもルルーシュの口を開かせようと質問を続けてくる。
「何を思い出していたんだ?」
と、尋ねられただけでルルーシュの心臓はドキリと跳ね上がった。
耳に響く優しいスザクの声。
ルルーシュは、低く甘いトーンで話すスザクの声が好きだった。耳に心地良いその声は今も変わらずルルーシュの胸を打ち震わせ、高鳴らせ、惑わせ――そして揺さぶり続けている。
負担を強いてしまうことは嫌というほど解っているのに、今すぐにでも全てを委ね、この心でさえも余すところ無く明け渡してしまいたい衝動に強く駆られてしまう。
関係を新しいものへと変えた今でさえ、まだ。……未だに。
(やめろ)
今の自分たちは共犯者であって、友達ではない。
己にそう言い聞かせながら、ルルーシュはスザクに対して無意識のうちに「そうだな」と答えていた。
けれども、鼓膜に届く自分の声は、何故か全く自分のものでは無いようにさえ思える。
水底で聞く音に、よく似ている。ただそう思った。
水中深く潜っている時のようにくぐもっていて、どこまでも静かで。――けれど。
(どうしてこんなにも遠い?)
一足先に、ルルーシュが十八歳になった誕生日。
今思えば、あの時が初めてだった。スザクと共に泣いたのは……。
続く言葉を探す頭が、ルルーシュ自身の意思とは全く無関係に回転を続けていた。秒針やマウス音にも似たデジタルチックな音が聞こえてくる。そんな妙な錯覚にさえ陥りそうだ。
――やがて、心と連携の切れた頭は勝手に答えを見つけ出し、ルルーシュへと差し出してくる。
ルルーシュは、いつのまにか唇を笑みの形そっくりに作り上げている自分に気付いた。
スザクに向かって微笑しながら、ルルーシュは言う。
「ちなみに、お前は七回だ、と。そう思っていただけだよ」
「えっ……?」
驚いたスザクが一瞬だけ大きく瞳を見開いた。その瞬間のみ、常の固さが剥がれ落ちている。
まだ表情豊かだった頃の片鱗を、ルルーシュは確かに垣間見た。
ほんの少しだけ覗く、懐かしいスザクの本質。一年前のスザクと重なるその姿を見て、ルルーシュの胸がズキリと痛んだ。
――こんな風に、頻りに在処を訴え続ける心がいつもルルーシュの邪魔をする。殺せるものなら殺してやりたいと幾度思ったか解らない。
けれど、いつも死なないのだ。何度打ち倒しても、凍らせても、この心という厄介な代物は。
スザクは緩んだ表情をすぐ元に戻した。取り繕った上でもまだ意外そうではあったが、スザクは仄かに苦笑しながら「そうだっけ?」と返してくる。
――涙が出るかと思ったが、出なかった。
(上出来だ)
ぼやけた思考の何処かでそんなことを考えながら深く息を吐き出したルルーシュは、足を組み替えてからのんびりとソファに凭れかかる。
「お前は泣き虫だからな」
不遜な調子でふんと鼻を鳴らしながら、ルルーシュはほとんど無意識に胸を反らしていた。
そして、誰に聞かせるでもなく胸の内で呟く。
(俺は正気だ)
意識は疾うにはっきりしている。……ほんの刹那、ぐらついていただけだ。
「そんなことはないよ」
スザクは即座に言い返してきた。その負けん気の強さも変わらない。
ともすればすぐにでも焼き切れそうになる神経を意思の力のみで押し留めながら、腕を組んだルルーシュは「そういうことにしておいてやるさ」と素っ気無く答えた。
ルルーシュは、スザクからは見えない角度で自分の腕を強く握り締める。
白く細長いその指先が、元々の白さを増すほどに強く。そして、よりきつく。
(馬鹿らしい。全く……どうかしているな、俺も)
時計の針は、進めるためにあるものだ。
『歴史の針を戻す愚を、私は犯さない』
自分が言ったことではないかと冷ややかに思いながら、ルルーシュは平然と前髪をかき上げた。
(スザクの泣き顔も、笑顔も、全て覚えているに決まっている)
ゼロ・レクイエムの詳細について話した時。黄昏の間で話した時。枢木神社で問い詰められた時。ブラックリベリオンでブリタニアへと連行された時。どうして俺を頼らないのかとルルーシュが詰め寄った時。
そして、一年前のバースデー。
巻き戻した時計の針を、ルルーシュはすぐに元通りの位置へとリセットする。
(やはり七回だ)
内心、記憶力は悪くない筈なのに、お互い自分のことを差し置いて、相手のことだけはよく覚えているものだとルルーシュは呆れていた。
まだテーブルの上に置かれている二つのグラスは離れたまま、けれど同じように透明な光を反射させている。
しかし、ルルーシュはそれでも、被った仮面のひび割れる音にだけは、とうとう知らん顔を貫いた。